西洋医学と漢方医学が融合した医療が重要 今津氏は、癌治療において西洋医学と漢方医学が融合したチーム医療が非常に重要であると考えている。しかしながら、多くの医師にとって、漢方はまだまだ「未知」であり、なかには漢方の効果をまったく評価しない医師も少なくないのが現状という。 その最たる原因は日本の医学部で漢方を勉強する機会がないこと、多くの医師が漢方ばかりか栄養学についても勉強していないことにある。そのため食養生や漢方という選択肢があることを多くの医師が軽視しがちという。 がん治療において、抗がん剤や放射線治療は確かに有効で、その効果を否定することはできない。しかし、問題はがん治療を受けたにもかかわらず、術後の対応や回復に満足できない患者さんが非常に多いことと今津氏は指摘する。 がん治療は長期戦、術後のケアが重要 せっかく手術をしても副作用に苦しみ、日常の生活の質(QOL)が下がってしまう。そこにアプローチできる有効な治療方法を西洋医学はあまり持ち合わせていない。 手術が成功し術後の経過が良ければ退院となるが、多くの患者は「退院後の食事は?」「入浴は?」「運動は?」と、日常生活をどう過ごすべきかに不安を抱えている。家族も同様。 この不安を払拭するための「養生訓」のような生活指導は漢方医学が最も得意とする分野であり、非常に効果的な緩和ケアができると今津氏。 西洋医学によるがん治療は外科治療(手術)、放射線治療、抗がん剤治療(化学療法)が三大療法であり、それぞれの治療が確立・推進されているが、QOL改善のための個人にあわせた術後対策や、副作用の標準的治療法は未だ確立されていない。 がん治療は長期戦で、術後のケアのほうが重要であるため、疾病ごとに患者さんを診断する西洋医学に留まらず、全体像(性別、年齢、体質、体力、季節、環境などすべて含む)を捉えて対応する漢方医学の療法からアプローチする新しい「統合医療やチーム医療」の果たす役割は非常に大きいと今津氏は強調した。 ここ5〜10年で、漢方薬が科学的に解明 近年は、徐々に漢方医学が臨床の現場でも用いられるようになっている。それは漢方の領域に科学的メスが入り、効果効能がより科学的に裏付けられてきているからだという。 例えば「大建中湯」という漢方薬は、1990年代後半までは「腸の蠕動運動を亢進する作用がある」という理解で、便秘や膨満感の時に処方されるに過ぎなかった。 しかしその後の研究で、この漢方薬には腸の蠕動運動を亢進するだけでなく、腸内血流促進効果、腸内温度改善効果などが科学的に明らかにされ、複数の明確な病態改善効果が示されている。 しかもこの研究は日本人医師チームによって行われ、今ではこの漢方薬が「腹が冷えて痛み、腹部膨満感がある」といった症状が診られた場合、保険適用で処方されることが当たり前になっている。また、腸閉塞やクローン病、潰瘍性大腸炎、頻尿にも活用され効果を発揮している。 つまりここ5〜10年の研究進歩で漢方薬が現代医学的に解明され、漢方治療の可能性がより高まっているという。 漢方薬を併用している患者は術後の経過が良い 今津氏がかつて所属していた慶応大学では、術後の経過について漢方薬がどのような役割を果たしているのか、いまから10年ほど前に今津氏が中心となって調査を行っている。 大腸がんの手術(開腹手術、腹腔鏡下手術等)を行った3,000人以上のカルテを調査したところ、術後、指定の西洋医薬品に加え漢方薬を服用しているグループとそうでないグループの比較では、漢方薬を併用しているグループのほうが退院が平均3日ほど早いことが明らかになったという。 
・
|
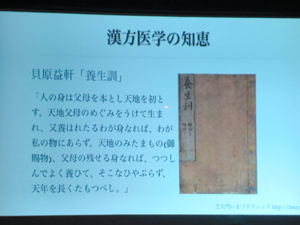
ただ、この調査では漢方薬が明らかに退院を早める要因になっているという確証は掴めなかった。退院を決めるのは主治医であり、主治医の判断と患者の意向によるため漢方薬が退院を早めることに役立ったという証拠はない。 しかし今津氏は漢方薬を併用している患者のほうが術後の経過が良いことを経験的に感じており、この調査結果により、漢方薬には副作用を緩和する役割があるのではないかと考えるようになったという。 漢方薬、がん治療の副作用を緩和 実際ここ数年で、いくつもの漢方薬に副作用緩和効果があることが次々と明らかになっている。例えば、大腸がんでは「フォルフィリ」という抗がん剤を用いるが、これを使用すると「手足のしびれと手足症候群(手足がパンパンに腫れて、指先の皮がむける、爪が剥がれるなど)」に苦しみがちだという。 他にも、副作用として、箸や鉛筆が持てない、歩行困難などもあり、日常生活に非常に大きな支障をきたすことがある。 しかも一般的に、抗がん剤の副作用は1回目より2回目、2回目より3回目のほうが酷くなることが多い。これは体内に抗がん剤が蓄積されてしまうからで、患者は抗がん剤治療を受ける度に、副作用に苦しむことになる。そこで、大腸がんで「フォルフィリ」による抗がん剤治療を受けることになったある男性に、「牛車腎気丸」という漢方薬を併用してもらった。 漢方薬、婦人科と産婦人科で多く利用 この男性も例外なく抗がん剤による副作用が1回目から現れ、手足が腫れ、痛みを訴えた。しかし2回目以降の抗がん剤治療時には、その痛みが軽減し、漢方薬を併用し続けることで、大きな副作用に苦しむことなくその後の抗がん剤治療を乗り切ったという。 他にも女性に多い乳がん、子宮がん、産後の肥立ちなどにも漢方薬は非常に相性が良いことを報告。例えば、乳がんではホルモン療法が一般的だが副作用としては更年期の症状に似た症状(ホットフラッシュやイライラなど)が起きる。 しかしこうした症状にも漢方は非常に高い効果を発揮する。実際、漢方薬が一番多く利用されている臨床の現場は婦人科と産婦人科であり、漢方薬は女性の不調と非常に親和性が高い。月経不順や無月経、PMS(月経前症候群)、不妊などにもリーズナブルに対応でき、しかも高い効果が現れる。その科学的メカニズムもどんどん明らかになっているという。 1,200年以上前から漢方は日本の医療で利用 いずれにせよ、漢方薬は西洋医学でカバーしきれない術後対策や副作用対策に非常に効果的である。西洋医学の現場に、少しずつ浸透し融合を深めている漢方医学だが、それをもっと現場で浸透させるために最も重要なことは、漢方薬に対する誤解を解くことだと今津氏はいう。 これは医師だけでなく、患者も同様である。漢方は中国から日本にやってきた。しかし、今から1,200年以上前、すでに日本の医療で用いられ、日本の風土や日本人の体質にあった日本独自の漢方がきちんと育っているという。 漢方の叡智、日本の医療に欠かせない 1,000年以上の時をかけ、育てられてきた日本の漢方の叡智は日本の医療に欠かせない。現代医学はガイドラインとEBM(evidence-based medicine 根拠に基づいた医療)の重要性ばかりを強調するが、やはり知識や知恵、経験も重要である。 1000年以上の歴史がある日本の漢方。その叡智が、がん患者の緩和ケアや副作用ケアに有効であれば、それを否定したり排除する必要はまったくない。漢方薬は今後科学的な裏付けとともにますます発展していくであろうと今津はまとめた。 ・
|
|

