食品添加物の安全性、「すべては量次第」
食品添加物や食品素材の専門誌として50年の歴史を持つ食品科学新聞社。同社発行の 「Food Style21」は機能性表示食品やサプリメントなどに特化した月刊誌で今年25周年を迎える。
機能性表示食品はすでに5000商品を突破しており、2021年度(2022年3月末迄)だけでも1,100件以上の登録があった。
石川氏自身は、2018年の1月から6月までの半年間で90kg(体脂肪27%)から73kg(体脂肪19%)の減量に成功したいう。 
・
|
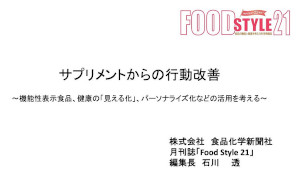
しかしこの「行動改善」は最も難しい。難しい点は大きく2つで「現状を認められない」と「続けられない」ではないか、と石川氏。 石川氏のように会話などがきっかけとなることもあるが、もう一つ有効なのが「健康の見える化アイテムの活用」ではないかと話す。 行動変容を促す大きなきっかけに
シンプルな機器を用いて、簡単にその場で現状を測定できて、他者と比較できるような「見える化」アイテムを利用することは、自分自身の現状を把握し、これはまずい!と行動変容を促す大きなきっかけになり得る。
このような、「健康の見える化」で、例えばファンケルでは尿検査の結果からサプリメントのパーソナライズ化も進めている。
|
|

