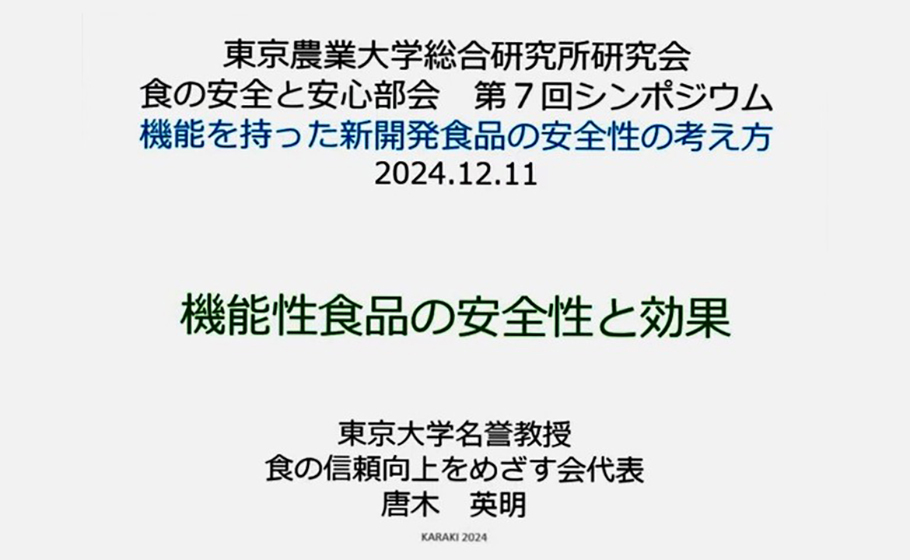
食品そのものの安全についてこれまで “食経験”をもとに判断されてきた部分が大きいが、新開発食品は多様化しており、食経験だけで判断できないものも増えている。本年度のシンポジウムでは新開発食品、特に生体への機能を持った食品の安全性をどのようにとらえていくべきかについて検討が行われた。ここでは東京大学名誉教授の唐木英明氏の講演を取り上げる。
機能性食品の安全性と効果
東京大学名誉教授 食の信頼向上をめざす会代表 唐木 英明
機能性表示食品の安全性とその効果について語ることが求められているが、唐木氏自身は薬理学者であり、長い間、健康食品について非常に懐疑的であったという。健康食品に何らかの効果があるのなら、それは医薬品にすれば良いわけで食品に機能や効果を求める姿勢そのものに否定的だったという。しかし2015年、機能性表示食品制度が立ち上がる際に、機能性表示食品の効果や安全性を担保するための事業がスタートしその委員に選出され、そこから健康食品について勉強をしていくと、いくつかそれまで見落としていたことに気がついたという。まず1つがプラセボ対象試験に対する考え方だ。医薬品の世界では当たり前に行っているプラセボ対象試験であるが、健康食品ではプラセボ対象試験が決して有効とは言えず、実際成り立たないケースが多く報告されている。つまり、健康食品を摂取しても摂取しなくても、健康効果がほとんどないのであればそれは有害とまでいかなくても不要なものである、と思っていた、と話す。また現在も厚生労働省や消費者庁の関連団体は同様の考えを持っている人が多いと指摘。
しかし、健康食品は実際多くの消費者が利用していて、セルフメディケーションとして利用している。ある調査では健康食品の使用経験について、国民の70%を超えていると報告している。市場としては十分に拡大し、関連企業も多い。それなのに効果があるのかないのかわからない、あるいは有害となってしまうと大きなギャップがあり、消費者はますます困惑してしまう。厚労省や消費者庁もHPなどで健康食品については「注意喚起」を呼びかける姿勢で、推奨はしていない。パンフレットも同様だ。どちらかというと「飛びつく前に考えよう」「安全とは言えない」「万人に効果が保証されていない」「専門家の評価が正しいとは限らない」「まずはバランスの取れた食事」などの文言が並び、適切な利用方法や効果的な利用方法については記されていない。業界団体さえ同じような姿勢だ。つまり、消費者が欲しい「有効性の情報」を手にすることは難しく、結局「宣伝を見て」という判断になりがちだ。これだけ健康食品が求められていて、セルフメディケーションが重要とされる時代に、健康食品の社会的意義に関する合意がない、ということが一番の課題ではないか、と唐木氏は指摘。実際、健康食品を活用している消費者の半数は効果を感じているから摂取し続けている、と回答している。リスクを説明するのは大切だが、リスクを強調しているだけの現状では、消費者のためにはならない。私自身も長い間、健康食品は無効でどちらかといえば有害と考えてきたが、おそらく、国も業界団体さえもいまだにそう考えているのではないか、と唐木氏。
健康食品の安全性を調査するにあたり、唐木氏自身が見逃していたと確信した点はプラセボ対象試験にあったという。多くの健康食品で有効性を示すことが難しいが、そもそも健康食品にプラセボ対象試験を用いることが間違いである、というのが薬理学者としての結論だと説明。現在健康食品のプラセボ対象試験は義務化されているが、正直どれほどの意味があるのか。そもそも健康食品のプラセボ対象試験は「被験者が正常な健康の人」になっている。医薬品のプラセボ対象試験は「病者」で行われるので有意差が出やすいが、健康食品の場合、健康な人同士で比較をしても差が出ないのは当たり前であるが、それが見落とされている。しかし機能性表示になって一部「軽病者」も被験者として認められるようになってからは明らかに有意差が出ている。次に予防効果については試験ができないということもある、と指摘。ワクチン一つとっても明確な予防効果を証明することは困難であることが医学の世界でも常識だ。つまり健康食品で予防効果を証明するのも不可能ということになる。そして3つ目に心因作用の評価ができない点にある。軽度な症状では心因作用の割合が大きいのは医薬品の世界でも同様で、プラセボ対象比較試験では差は得にくい。実際、軽度のうつ病、不安神経症、狭心症、認知症、季節性アレルギー、睡眠、不安、疲労、ストレス、血圧、体温、便通などはプラセボ群で大きな改善が認められたり、治療効果が小さかったり、大きなばらつきが確認されている。しかし標準治療に用いられる薬剤が有効であることは、それを支持する数多くの試験があるからにすぎない。しかし、機能性表示食品の届出から求められている健康食品は睡眠、不安、疲労、ストレス、鬱、血圧、体温、便通など、まさに薬理効果でさえ曖昧な症状と一致している。 現在、機能性表示食品に関する質疑応答集でも例外を認めずプラセボ対象試験を義務化しているが、これは有意差が得にくいだけでなく、逆に有意差が出た場合にそれが不適切に活用されることも考えられる。そもそも健康食品と医薬品の効果判定は異なるべきであるし、「トクホ」があることで、健康食品の評価がより複雑でわかりにくくなってしまっている。国は「安全性」を検討することに終始し、不適切な試験を強要することで「無効」や「危険」の誤解を拡散することに加担し、消費者に理解できない複雑な制度や企業が負担になるようなルールばかり増やしているが、これでは「消費者が求めているセルフメディケーション手段」の普及や活用につながらないのではないか。サプリメントや健康食品は、機能性表示やトクホなど4つにも分類せず、ひとまとめにした新たな法整備が必要な段階にきているのではないか、と唐木氏は訴えた。








