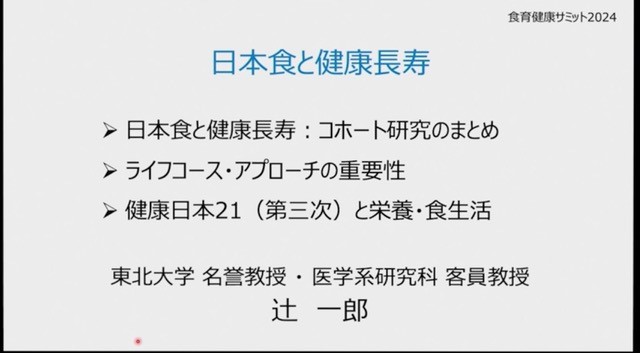
2024年12月4日〜2025年2月28日まで、オンラインで「健康サミット2024」が開催されている。このシンポジウムでは「健康寿命延伸に向けたアプローチ~高齢期をいきいきと過ごすための食事と運動~」をテーマに、健康寿命の延伸に向けた具体的な対策として、食事によるフレイルやサルコペニア予防、日本型食生活の意義などについて、複数の専門家による講演が行われている。ここでは東北大学 名誉教授・医学系研究科 客員教授 辻一郎氏による基調講演「日本食と健康長寿」を取り上げる。
東北大学 名誉教授 / 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 客員教授 辻一郎
食事と栄養の捉え方
食事や栄養を考える際、大きく3つの捉え方がある。1つ目は、「栄養素」で、タンパク質、脂肪、炭水化物、ミネラル、ビタミンなど、食品に含まれる成分を指す。2つ目は、それらの栄養素が含まれた「食品」の単位で考える方法で、肉、魚、野菜、果物など「食品」を丸ごと摂取することで健康にどのような影響があるのかについても、近年多くの研究が行われている。そして3つ目は、食品を組み合わせた「食事パターン」として捉える方法で、例えば、和食、洋食、地中海食などについて研究が進んでいる。辻氏らのグループでは、宮城県大崎市を中心とする地域住民の中高年、約5万人を対象にしたコホート研究を行った実績があるが、この研究でも、食事に関するアンケートを基に食品摂取頻度や栄養摂取量だけでなく、「食事パターン」を調査することで健康への影響を分析したという。この調査で「緑茶の摂取頻度と死亡リスクの関係」を調べたところ、循環器疾患による死亡リスクは、緑茶摂取頻度が高いほど有意に低下することがわかり、一方でがん死亡リスクに関しては、統計的な有意差は見られなかったことを報告。また、みかんの摂取頻度が高いほど、すい臓がんや前立腺がんのリスクが約4割低下することも確認された、と報告。魚の摂取頻度についても、頻度が高い方が認知症の発生リスクが有意に低下することが確認され、魚をほぼ毎日食べる人は、摂取頻度が少ない人に比べて約16%認知症リスクが低いという結果がでたと解説。
食事パターンの意義
これらの食品単体の分析に加えて、食品の組み合わせ、つまり「食事パターン」に注目する研究は世界でも行われていて、これまで特に「地中海食」が健康に良い食事パターンとして世界的に注目されている。これはギリシヤやイタリアなど地中海沿岸諸国で虚血性心疾患に罹患する人が少ないという理由から、ハーバード大学のウィレット教授が1990年に研究をスタートさせたことで有名になった。地中海食の特徴は、野菜、果物、穀類、オリーブオイル、豆類を基盤とし、魚介類を週2回以上摂取することにあり、赤身肉やお菓子の摂取は控えめで、適度な量の鶏肉や乳製品を取り入れることも重要とされている。また地中海食では果物やナッツ類、オリーブオイルが豊富に摂取できるのも特徴だ。長寿の国として日本食についても同様に注目が集まっており、辻氏らのグループでも研究を進めているが、米、味噌汁、魚、野菜、海藻、漬物、緑茶などを中心とした食事が総死亡リスクや認知症リスクの低下に寄与することがわかってきている、と報告。辻氏らのグループでは、日本食パターンを得点化する方法を開発し、総死亡リスクや認知症リスクとの関連を調べているという。実際、1994年と2006年の2回、それぞれ3000名の65歳以上を対象に食事パターンによる調査を行ったところ、日本食パターンの得点が高いほど、認知症リスクが有意に低下することが確認された、と解説。また、日本食パターンを使ってはいないが、国立長寿医療研究センターが行った久山町研究では、食品摂取の多様性(様々な種類の食品を摂取すること)も重要な要素であることが報告されている。この研究では食品の種類が多いほど、認知症や生活習慣病のリスクが低下することが明らかになったと解説。同じくこの研究ではMRI(磁気共鳴画像)も用いて、食品の多様性が高いほど脳の海馬の縮小が少ないことも確認されたと解説。これらの結果からも日本食と認知症リスク低下との間には一定の因果性が示唆される。しかし、日本食の優れたエビデンスに対し、日本人の日本食離れが進んでいることが課題だ。米や魚、野菜の摂取は減っているのに牛肉や豚肉の消費は増えていて、またファーストフードの普及など日本人の食生活は大きく変化している。
健康づくりの政策
国内では現在「健康日本21」の第3次計画が進行中で、この計画では、生活習慣病予防や健康寿命の延伸を目指し、バランスの良い食事の普及、野菜摂取量の増加、食塩摂取量の減少などが目標に掲げられている。また、幼少期から高齢期までの生涯を通じた「ライフコースアプローチ」に基づく健康づくりが推進されている。具体的には、例えばバランスの良い食事、つまり、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日という方の割合を令和14年度には50パーセントにまで上げる、野菜摂取量の平均値を350グラムに、果物摂取量の平均値を200グラムにまで増やす、 食塩摂取量の平均値を7グラムまで減らすといった目標が設定されている。日本食の摂取量が減っていることは指摘したとおりで、この対策としては特に学校給食の場で日本食の良さを伝える取り組みや、自然と健康になれる社会環境を整えることが重要視されており、それを子どもたちが家庭に持ち帰ったり、あるいは次の世代に引き継いでいくことも期待されている。とはいえ健康的な日本食の普及については、食品製造業や流通業、行政、メディアが協力し、人々が健康的な食生活を選びやすい環境を作ることが求められているのではないか、とまとめた。

20230804_ウエルネスフードジャパン2023_21世紀はみみずが人類を救う-1200x900.jpg)
20230213-27_食品開発展プレゼンフォートナイト2023冬-1200x694.jpg)





