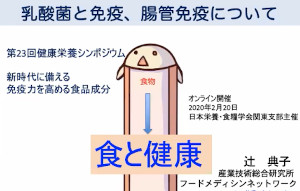の中の食品免疫〜美食が健康を作る〜-1200x691.jpg)
十文字学園女子大学 食品開発学科 教授 日本大学医学部 粘膜免疫・共生微生物学分野 客員教授 辻 典子
2025年3月17日(月)、オンラインにて第26回国際おやつ研究会オンラインセミナーが開催された。今回は「ガストロノミー(美食医)の中の食品免疫~美食が健康をつくる~」をテーマに十文字学園女子大学の辻典子氏が講演を行った。ガストロノミーとは一般的に食事と文化の関係性のことであり「美食」と定義されるが、食には健康効果や食事療法があることを加え、より包括的に捉えていくことでガストロノミーがより発展していくのではないか、と辻氏は述べる。
そのための提案としてまずは「地産地消などで付加価値をつけるだけでなく、食品による免疫機能効果のモニタリングもする」と良い、と辻氏。食と免疫は関係している。免疫は特に腸管が大きく関与している。私たちが食品からさまざまな栄養素を摂取すると、まずは小腸のあたりで免疫機能が刺激され、さらに成熟し、選ばれた腸内細菌は大腸に到達すると非常に多様な腸内フローラのコミュニティを作る。つまり、私たちが日々の食事で「何を食べるか」「何を選ぶか」によって、加齢とともに老化する「免疫老化」を抑制できることが、さまざまな食品研究によって明らかにされているのだ。超高齢化社会において「個別医療」の実現やその技術に注目が集まるが、加齢やストレスなどで低下する免疫機能を食事で制御することも必要なアプローチではないか、と辻氏。「食による免疫のモニタリングシステム」が普及すれば、一人ひとり異なる腸内環境に応じた免疫細胞への適切なアプローチも可能となるだろう。そうすれば自然免疫を活性化することを目的とした食品開発も実現するはずだ。
そもそも私たちの体の免疫は大きく「自然免疫」と「獲得免疫」に分けられるが、それぞれの免疫機能を正常に働かせるためには、私たちの全身に存在する免疫細胞である「マクロファージ」の働きを高めてくれる「糖質類(リポポリサッカライド)」を含む食品を積極的に取り入れることが有効であることが解明されている。食品成分が免疫システムに対して作用する場所は「小腸」だ。小腸の主要な常在菌は乳酸菌で、私たち日本人には馴染みのある発酵食品にも豊富に含まれる乳酸菌や微生物が、小腸において抗炎症作用を発揮することに役立っている。食事からどのような成分や菌を摂取するかによって、免疫機能の主軸とも言える小腸の環境は左右され、小腸の環境が直接「免疫機能の質」に関与している。例えば、日本の伝統的な発酵食品の代表である味噌を摂取すると、小腸では樹状細胞が増強されることがわかっているし、味噌には乳酸菌・酵母・麹菌なども含まれるが、この豊富な核酸・多糖が共闘して免疫細胞を活性化していることもわかっている。同じく納豆菌にも樹状細胞からのサイトカイン産生活性が確認されている。このように、一部の食品によって小腸で免疫増強スイッチがオンになり、免疫機能の成熟に貢献していることは間違いない、と辻氏は解説。
他にも、高齢のマウスや腸管免疫の老化を促進させたモデルマウスでは、腸管内のT細胞の数が通常マウスの数分の1程度に低下してしまうが、乳酸菌を2週間経口投与することでT細胞の数はスピーディーに回復し、免疫老化マウスであっても食(乳酸菌)の介入で、通常のマウスと同じくらいまでT細胞だけでなく免疫全体の回復が見られた事例についても紹介。また、水溶性食物繊維は、大腸ではなく小腸で自然免疫を活性することがわかってきており、水溶性食物繊維に限らず多糖類は体内の自然免疫のレセプターを活性することが確認できている。食品免疫学的にメリットのあるものを積極的に選んで摂取することで、免疫環境を高められることは間違いない。発酵食品、果物、食物繊維、短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、ビタミン類、アミノ酸、ハーブや、これらに共生する微生物は食薬素材と言える。これらの食薬素材が腸管に消化吸収されたのち、腸管バリアや免疫機能にどのような影響を与えるか、個別に評価できるところまできている。 このような研究をベースに、腸内細菌叢を指標とした「食と免疫」のガイドラインが作成できれば、地域の伝統食や日本の伝統的な食品成分をこれまで以上に健康の維持増進に役立てられるだろう。私たちが生体機能を適切に維持していくためには「一生を通じて」食品による腸内細菌の適切な刺激や環境維持が必要であることがわかっている。一人ひとりの免疫機能の「見える化」が進み、免疫機能の計測が一般化して社会に根付けば、免疫・生活レベル・健康レベルはさらに向上する。それを実現する食のあり方こそ「次世代型ガストロノミー」ではないか、と辻氏。特におやつにはそのポテンシャルが高く内在している。おやつの場合、消化器官だけでなく感覚器官に与える影響も大きい。一人が健康というだけでなく、その地域、つまりコミュニティ全体が健康であるということを目指す場合、免疫や地産地消は良い切り口になるはずだ。次世代型ガストロノミーの実現に向けて、さらなる研究を続けたい、と話した。

20230720_腸内環境のキープレイヤー「短鎖脂肪酸」がもたらす健康効果とその展望.jpg)