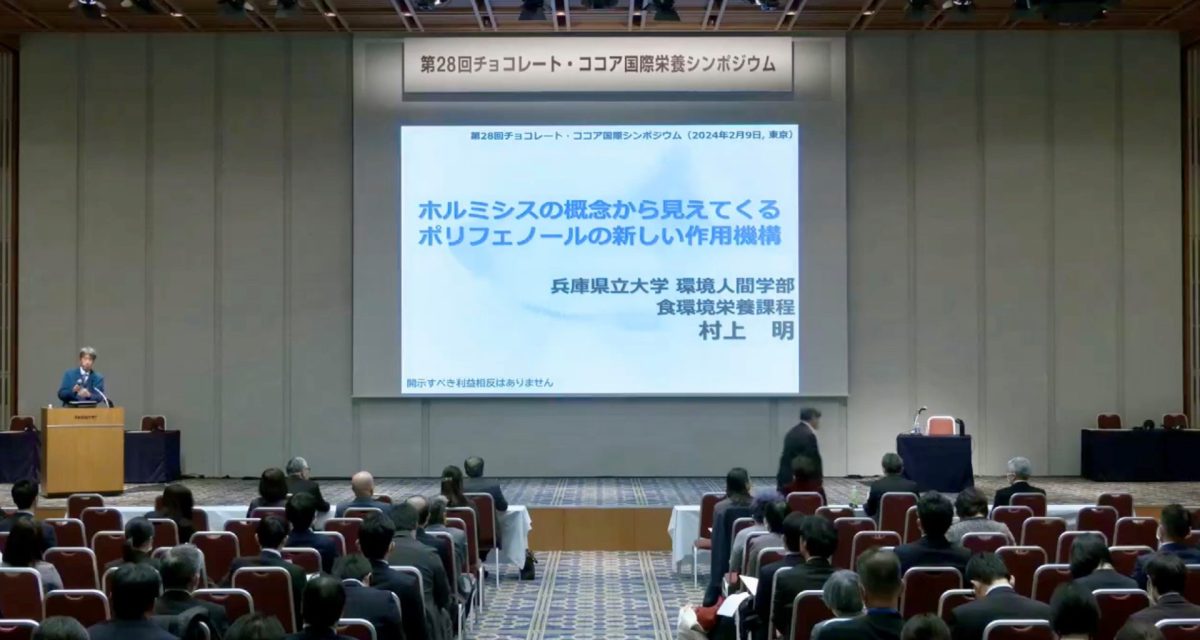2025年5月22日(木)東京ビッグサイト会議等にて、「カロテノイドフォーラム」が開催された。機能性素材として人気の高いカロテノイドの分析法や機能性などについて、最新情報が各研究者より発表された。ここでは、名城大学 大学院総合学術研究科 理工学部化学教室 准教授 本田真己氏による「次世代型“シス型”カロテノイドの実用化に向けた取り組み」を取り上げる。
名城大学 大学院総合学術研究科 理工学部化学教室 准教授 本田真己
カロテノイドの異性化に関する取り組みとその応用について、本田氏らの研究グループでは、分子内に二重結合を有する脂質成分、特にカロテノイドの異性化を中心とした研究を行っている。加えて、最近ではポリフェノール類や脂肪酸の異性化に関する研究も進めているという。
天然のカロテノイドは現在850〜1000種類程度発見されている。これらは主にオールトランス型として存在しているが、本田氏らの研究グループではこれらを「シス型」に「異性化」させる技術開発に成功し、得られたシス型カロテノイド成分の生理活性や物性の違いを評価しているという。
そもそも植物や微生物に存在するカロテノイドはすべてオールトランス型で存在するのに、加工食品や動植物の体内においては二重結合の一部がシス型に異性化されたカロテノイドが少量であるが存在している。これは、私たちの体内にカロテノイドをシス型に変えるメカニズムがあるか、あるいは食品を加工する過程の中でシス型に異性化する鍵があると考えられているが、まだ解明されていない点が多いという。いずれにせよ、シス型のカロテノイドはオールトランス型よりも吸収率や融解率が高いことがわかっているため、このシス型カロテノイドが活用されれば、食品の高機能化や加工効率の向上の実現につながると考えられる。具体的には、体内吸収性の改善、有用成分の機能強化、毒性の低減、そして生産工程の簡素化や環境負荷の低減といった応用も期待されるだろう。
カロテノイドは現在、食品や化粧品、飼料といった分野で広く活用されており、その市場規模も年々拡大していて非常に需要の高い機能性成分の一つとなっている。カロテノイドの中でもアスタキサンチンやルテインなどは機能性の高さから特に注目を集めており、近年は微生物によって生産されたオーガニックなカロテノイドの需要も高まっている。また、カロテノイドをもっと身近な成分にするためには溶解率を高めることで、生産工程の簡素化が実現し、グリーンラベルに貢献できる。
天然のカロテノイドの構造的特徴は、長い二重結合鎖が挙げられ、この構造により一重項酸素(活性酸素)を消去する力が非常に高いことがわかっており、私たち人や動植物の体内で抗酸化作用を発揮している。しかしながら、一般的な植物に含まれるカロテノイドは全てオールトランス型で、オールトランス型のカロテノイドは結晶性が高いため、油脂や水への溶解性が極めて低く、体内吸収性や加工効率に課題があり、天然のカロテノイドの摂取ではカロテノイドの機能が十分に得られないのではないか、という疑問が兼ねてから指摘されている。
一方で、トマトソースなどの加工食品や私たちの体内で検出されるカロテノイドには一部シス型のものが存在している。つまり、わずかなシス型のカロテノイドに機能性の秘密があるのではないかと着目し、本田氏らの研究室ではオールトランス型カロテノイドをシス型に異性化することを試みたという。すると、シス型のカロテノイドは結晶性が明らかに低下し、オイル状またはアモルファス(非結晶)状態になるため、各種溶媒への溶解性が飛躍的に向上し、例えば、トマトに含まれるカロテノイドのリコピンも異性化することで6000倍以上の溶解度改善が確認されている、と報告。
さらに、シス型のカロテノイドは体内での吸収性や蓄積性が高く、細胞試験でもトランス型よりも高い生理活性が示されている、と解説。特に、エラスターゼ活性阻害やメラニン生成抑制といった作用が強く、抗炎症作用や抗がん作用、抗肥満効果なども確認できた。
オールトランス型のカロテノイドを異性化する方法は、加熱や光照射、触媒の使用などがあるという。特にフローリアクターを使った連続式加熱法は、短時間・高温処理で効率的に異性化を進行させ、しかも成分の劣化が少ないという利点があるという。また、ニンニクや玉ねぎといった食材に含まれる硫黄化合物が異性化を促進することも明らかになっており、これは地中海料理が長寿食に貢献している理由の一つと言える可能性があるのではないか、と指摘。本田氏らの研究グループではこれらの知見をもとに、シリカゲルに異性化触媒を固定化した不均一触媒を開発し製品化を進めているという。
さらに、アスタキサンチンやリコピンといったシス型カロテノイドを純度98%以上で生成し、動物試験を行ったところ、シス型はトランス型に比べて数十倍から数百倍の吸収率を示すことが確認されているという。特に「13-シス体アスタキサンチン」では428倍という驚異的な数値を記録したという。
このシス型カロテノイドをどのように応用するかについて、食品や化粧品に添加して機能性を高めるだけでなく、水産や畜産の飼料にも期待が寄せられているという。シス型アスタキサンチンを鶏や魚に給与した実験では、卵黄や魚肉の色上げ効果が顕著に向上し、含有量も大幅に増加しているので、機能性食品の開発に役立つことが推測されるだけでなく、例えばエビやシャケなどの見た目の向上にも容易に貢献できるだろう。 シス型カロテノイドの実用化に向けた課題としては、安全性の確保がある。基本的にはシス型のカロテノイドは、量は少ないが動物に含有されている天然素材のものと同等であるため、基本安全だと考えられるが、高濃度のシス型についてはこれからヒト臨床試験などを行い安全性を担保することが求められる。また、シス型が体内でどのように作用機序を発揮するのかを分析する技術の確立も必要だ。そしてトランス型カロテノイドの異性化技術のスケールアップや製品の安定化などが挙げられる。現時点ではリコピンやアスタキサンチンについては一部安全性評価が終了していて、今後さらなる評価を進められる予定だと話した。