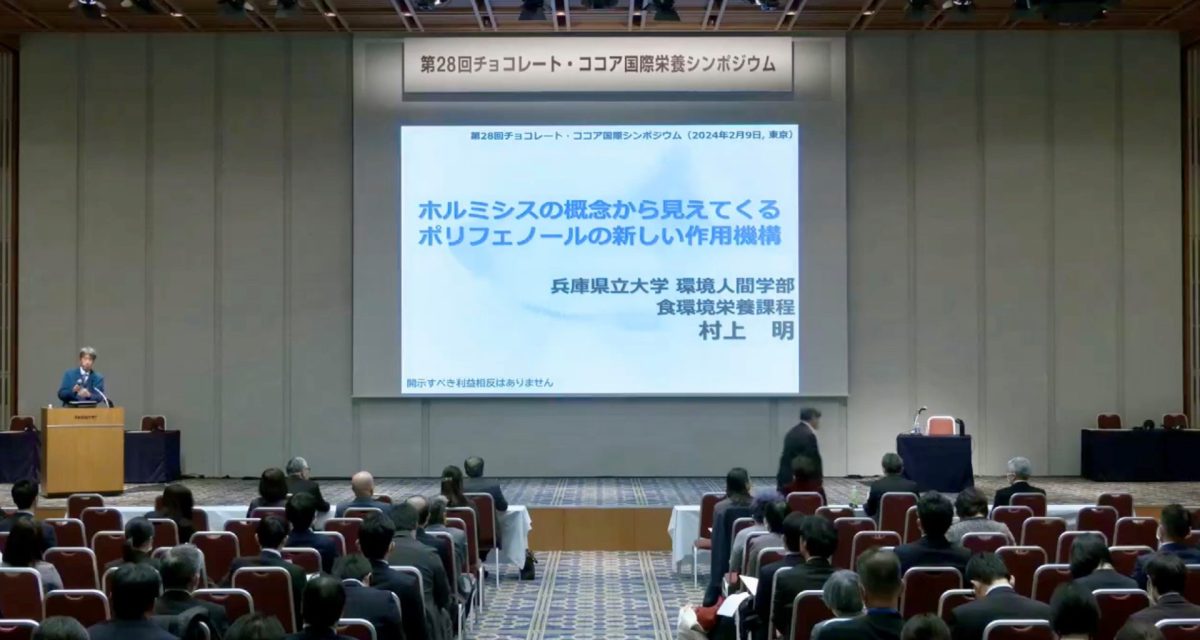2025年5月22日(木)東京ビッグサイトにて「ifia JAPAN(第27回国際食品素材/添加物展)」が開催された。加工食品の製造において食品素材や添加物は必要不可欠で、現在は食品の機能性だけでなく、製造におけるサステナビリティやSDGsなどを意識しながらより良い加工食品を製造開発することが各企業に求められている。ここでは「SDGsに貢献できる食品添加物・機能性素材・未利用資源セッション」から共同船舶株式会社による「海のSDGs「鯨」と鯨肉の機能性について」を取り上げる。
海のSDGs「鯨」と鯨肉の機能性について 共同船舶(株)
若い人に捕鯨についてどのような印象を持っているかを調査すると「鯨を獲っていいのか?」と指摘する人がほとんどだという。基本的に、商業捕鯨については捕獲対象となる鯨の種類と頭数が厳格に定められている。例えばミンククジラは約2万頭生息しているのに対し、捕獲可能量は144頭(0.69%)まで、ニタリクジラであれば約1万6000頭生息しているのに対し捕獲可能量は153頭(0.93%)といったように、捕鯨可能な鯨の種類、頭数は全て定められているそうだ。そのため捕鯨に関するこれまでの資料を遡っても、この100年で鯨の種類や頭数は原則変わっていない。そして、捕獲された鯨は国内では鯨類研究所にその遺伝子が登録されるというルールがあるので、提供している鯨肉を持っていけば、その鯨はいつ誰が捕獲したかもわかる仕組みと、密漁できない仕組みが確立されているという。つまり、漁業の中でも、生産管理、資源管理、トレーサビリティ管理が最も確立されているのが商業捕鯨であると解説。もちろん南極海のシロナガスクジラのように少ない頭数しかいないものは捕獲することはない。
さらに「鯨を食べたことがない、食べる必要がない」という意見も若い人を中心に多い、と話す。鯨は毎日、自分の体重の4%程度の食事をしており、日本鯨類研究所の推計では、鯨が1年間に食べる水産資源の量は人間の年間漁獲量の3〜6倍で、つまり鯨は食物連鎖の最上位に君臨するため、鯨だけを過剰に保護することは逆に海洋生態系のバランスを崩すことにつながる、と解説。国連が掲げるSDGsの中に「海の豊さを守る」とあるが、捕鯨は地球環境の保全という大きな役割も担っているという。豚や牛、鶏などの食肉1キロを生産するために必要な穀物は牛で12キロにもなるが、鯨の場合そのようなデメリットはなく、一頭捕鯨すれば、年間でその体重の約15倍の餌となる水産資源が人類のために利用可能になる、と解説。
そして鯨肉を食べることには利点が多いという。まずは魚を生で食べるという日本の食文化に貢献できる点であろう。生で魚を食べる場合、アニサキスの心配があるが、鯨肉にはアニサキスの心配がないと説明。アニサキスはサバやアジなどに寄生し、主に生で食べた時に当たると強烈な痛みや嘔吐を引き起こすが、アニサキスにとって鯨やイルカは最終宿主であるにも関わらず、鯨の場合、アニサキスが消化器官以外で発見された事例がなく、鯨肉を生で食べてもアニサキス症を引き起こすことはないという。しかし、アニサキスの最終宿主は鯨であり、アニサキスは鯨やイルカの消化管の中でしか成虫になれないし、成虫になれないと卵も産めない。鯨の中にいるアニサキスは鯨の消化器官の中で成虫になり、消化器官の中で成熟したアニサキスの親が卵を産むが、この卵は鯨の排泄物と海水中に放出され、オキアミなどに食されることで、オキアミを食べるサバ、アジ、イワシなどの体内で幼虫となり、それを人が食べることでアニサキス症が起こる。つまり、鯨が増えることはアニサキスが増えることにもつながり、私たち日本人が好む「刺身」の食文化を守るためにも、適度な捕鯨は必要だと説明した。
このように、豊かな海を守るとともに、豊かな食生活を守るために捕鯨は重要なだけでない。鯨肉の機能性についてもぜひ注目してほしいと話す。鯨肉には驚異的な量の「バレニン」が含まれているという。鯨の赤身肉は高タンパク質で低カロリーであることが知られるが、このバレニンは第3のイミダゾールペプチドとされ、鯨の「抗疲労成分」として注目されている。鯨は6000キロなど長距離を絶食・不眠で泳ぐが、この体力を支えているのがカルノシン、アンセリンといったイミダゾールペプチドで、さらにバレニンは他の回遊魚にはみられない、鯨特有のアミノ酸結合体成分であるという。私たちがバレニンを摂取することで「認知症予防改善」「糖代謝促進」「筋損傷の修復・肥大化」「骨形成促進」「脂肪細胞分解促進」「がん細胞増殖抑制」「免疫力亢進」などの効果が得られることが確認されているが、これはバレニンの摂取によってホルモンやタンパク質であるさまざまなマイオカインが分泌されることで、さまざまな遺伝子が体内で発現することによって得られる効果だと考えられているという。
特に、高校生や大学生など若年層で部活動などの運動をしている人や、勉強に集中している学生などへのバレニンの効果を計測するため、高校1〜2年生350人に鯨肉から抽出したバレニンのサプリメントを4週間摂取してもらったところ、アンケート調査ではあるが、「睡眠の質の向上」「集中力UP」「疲労感の改善」などに有意な評価が得られ、一方で、摂取をやめると集中力の向上は54.2%から35.3%まで大幅にダウンしたと説明。現在はバレニンの「寿命」についての研究が行われていて、平均寿命1ヶ月の線虫の23日目生存率をバレニン投与ありとなしで比較したところ、バレニンありのグループの線虫は80%の生存率だった(一方、バレニンなしの生存率は40%)と報告。線虫の大きさや運動量もバレニンありの方が数値は大きくなり、バレニンありの線虫の遺伝子解析を行ったところ、若返り遺伝子として知られる「サーチュイン遺伝子」の発現が確認できたという。人の場合でも同じような効果が得られるのか、二重盲検プラセボ対照比較試験を行ったところ、バレニンの摂取で、人でもサーチュイン遺伝子(サーチュイン1)が発現したことが確認できたという。今後商品化を進めるかどうかのレベルには至っていないが、鯨肉の健康効果が高いことは間違いなく、多くの人にぜひ食べてもらいたいと訴求。さらに滅多に市場に出回らないが鯨の皮にはオメガ3がリッチに含まれていて、剃毛したマウスに鯨由来のオメガ3(鯨油)を塗布することで有意な育毛効果が確認できたという。これは、鯨油の塗布により、塗布した部分の毛細血管の中に血流量を上げる遺伝子が発現するからで、これについては特許申請中で商品化を検討しているという。 鯨料理は日本では室町時代には登場しており、江戸時代には庶民の食べ物として鯨食文化が全国各地に根付いていた。そして捕鯨も日本の伝統文化の一つと言える。現在は、鯨肉は高級食材になってしまい、日常の食事からは遠ざかっているが、全国各地に鯨食の文化が受け継がれているのでぜひ食べてみてほしいとまとめた。