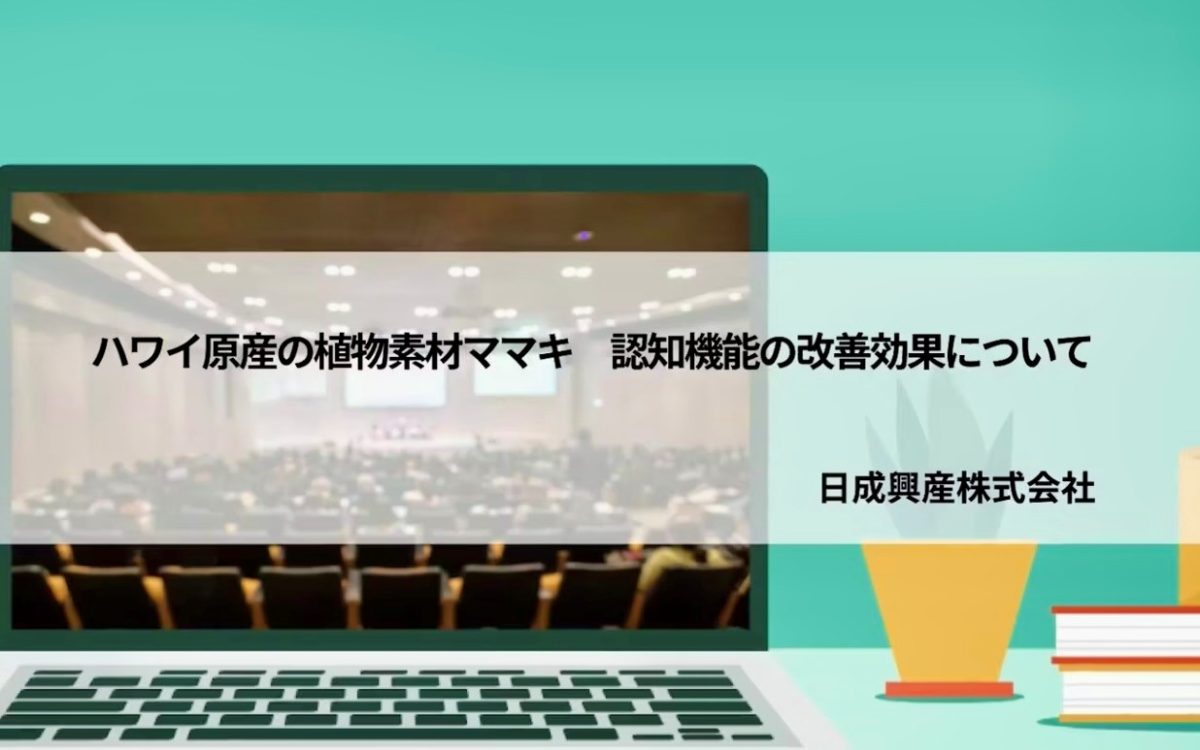
2025年6月16日(月)〜6月27日(金)、オンラインで「食品開発展プレゼンフォートナイト」が開催された。食品開発展プレゼンフォートナイトでは、オンライン上で機能性素材や新技術などのプレゼンを聴講できる。ここでは日成興産株式会社による「ハワイ原産の植物素材ママキ 認知症機能の改善効果について」を取り上げる。
日成興産株式会社
日本では少子高齢化の進行に伴い認知症患者が激増しており、特にこの数年深刻な社会問題となっている。認知症とは、加齢により脳の神経細胞が死滅し、それに伴い脳に器質的な異常が起きることで、正常に発達した知能や知性が不可逆的に低下していく「状態」を指す。そして一般的に広く「認知症」という言葉が使われているが、これは医学的な正式病名ではなく、複数の症状の総称であることも理解しておく必要がある。そして、主な認知症として「アルツハイマー型」「レビー小体型」「前頭側頭型」の3種類があることも近年は理解されるようになっている。これらはいずれも、脳内に異常タンパク質が蓄積することにより発症するという共通点がある。具体的には「アルツハイマー型ではアミロイドβおよびタウ」「レビー小体型ではα-シヌクレイン」「前頭側頭型ではTDP-43およびタウ」がそれぞれ異常に蓄積することが原因と考えられている。
そして、認知症の種類ごとに主な原因となるタンパク質が異なる点が、認知症の医薬品開発における最大のハードルになっている。つまり、予防や治療を行う際には、それぞれのタンパク質の蓄積を抑制する必要があり、理想的には、4種類すべてに作用する成分が望ましいが、現時点ではアルツハイマー型認知症においてアミロイドβを脳から除去する薬が承認されているのみだ。前述のとおり認知症は多様な原因タンパク質に起因するため、アルツハイマー型の治療薬を摂取しても他の型に効果が及ばない。さらに現在承認されている治療薬は点滴投与を前提とし、年間の自己負担額も高額で一般的な予防手段にもなりにくい。
認知症の原因となるタンパク質は、発症の数十年前から脳内で蓄積がはじまっていることが知られている。そのため、早期の段階で予防や治療を開始する必要があるが、現実には一般人が日常的に使用できる製品が少ない。またこのような背景があるからこそ、毎日手軽に摂取できる「予防」に役立つサプリメントや食品が求められている。
こうした背景の中で、注目を集めているのが「ママキ」という植物である。ママキはハワイ諸島にのみ自生するイラクサ科の植物で、現地では古来より乾燥させた葉がお茶として飲用されてきた。また、ママキの果実も食用にされている。日本国内では「ママキ茶」として販売されており、主成分としてカテキン、クロロゲン酸、ルチンといった3種のポリフェノールが含まれている。抗ストレス、抗疲労、抗炎症などの効果があるとされ、特に現地のハワイでは天然の民間薬としての歴史も長い植物だ。
近年、大阪公立大学の富山教授らの研究によりこのママキにはアルツハイマー型、レビー小体型、前頭側頭型の3種類すべての認知症に効果がある可能性が示されている、と説明。富山教授らの研究では、ママキの抽出物や粉末を各認知症モデルマウスに経口投与し、その認知機能への影響を評価している。その結果、マウスにママキを1日100マイクログラム、1ヶ月間投与することで「アルツハイマー型について:脳内のアミロイドベータ沈着およびオリゴマーが大幅に減少」、「レビー小体型について:アルファシヌクレインおよびリン酸化体の沈着が視覚的に明らかに減少」、「前頭側頭型について:タウおよびTDP-43の蓄積が抑制され、ポリGAやポリGPなどの異常ポリペプチドも減少」という変化が確認できたという。また、これらの変化はいずれも経口投与によってもたらされたもので理想的である、と説明。さらに富山教授らはママキの作用機序に「腸脳相関」が関係している可能性を示唆している、と解説。腸脳相関とは、腸と脳が双方向に影響し合う現象を指し、腸は迷走神経を通じて脳とつながっており、ホルモンやサイトカインを介して情報を伝達していることが解明されている。ママキの作用機序についてはほとんど何もわかっていないのが現状であるが、おそらく「腸脳相関」が関係しているのではないかと考えられる。
腸内細菌叢が脳に与える影響は、複数の研究や試験で裏付けられている。例えば九州大学では、腸内に細菌を持つSPFマウスと、菌を持たないGFマウス(無菌マウス)にストレスを与え、HPA軸(視床下部-下垂体-副腎軸)を通じたホルモン分泌の差異を測定した。その結果、GFマウスではストレス応答が過剰であり、腸内細菌叢の存在が脳のストレス耐性に関与することが示されている。過去の研究では、富山教授による生薬成分の経口投与により、認知症モデルマウスの認知機能が改善された例も報告されている。この実験では、経口投与と皮下投与を比較した結果、経口投与に顕著な効果が見られ、腸内細菌が有効成分の代謝に関与している可能性が示された。さらに、糞便移植により腸内細菌叢の変化させることで、認知機能にも変化が生じることが分かっている。具体的には、認知症モデルマウスに健康なマウスの糞便を移植したところ、認知機能が改善された。一方、健康なマウスに認知症マウスの糞便を移植した場合、わずかではあるが認知機能が低下した、という結果だ。これらの研究結果から、植物由来成分が経口投与によって腸内環境を改善し、結果的に認知機能に良い影響を与えていることが推測される。点滴ではなく、食品として経口摂取できるという点は予防において最大の利点だ。 認知症は種類ごとに原因タンパク質が異なるが、ママキは、アミロイドベータ、アルファシヌクレイン、タウ、TDP-43といった複数の原因タンパク質の蓄積を抑制する作用があることが確認されており、現在日成興産ではセーブロファーマ株式会社と共同でママキを用いたサプリメントの開発を進めているという。将来的にはヒト臨床試験を経て、安全性と有効性を確認した上で、広く普及させることを目指している、と報告した。


20221130_第2回-国際発酵・醸造食品産業展 生鮮食品を含む機能性表示食品制度への期待と今後の展望(農林水産省)-1200x723.jpg)





