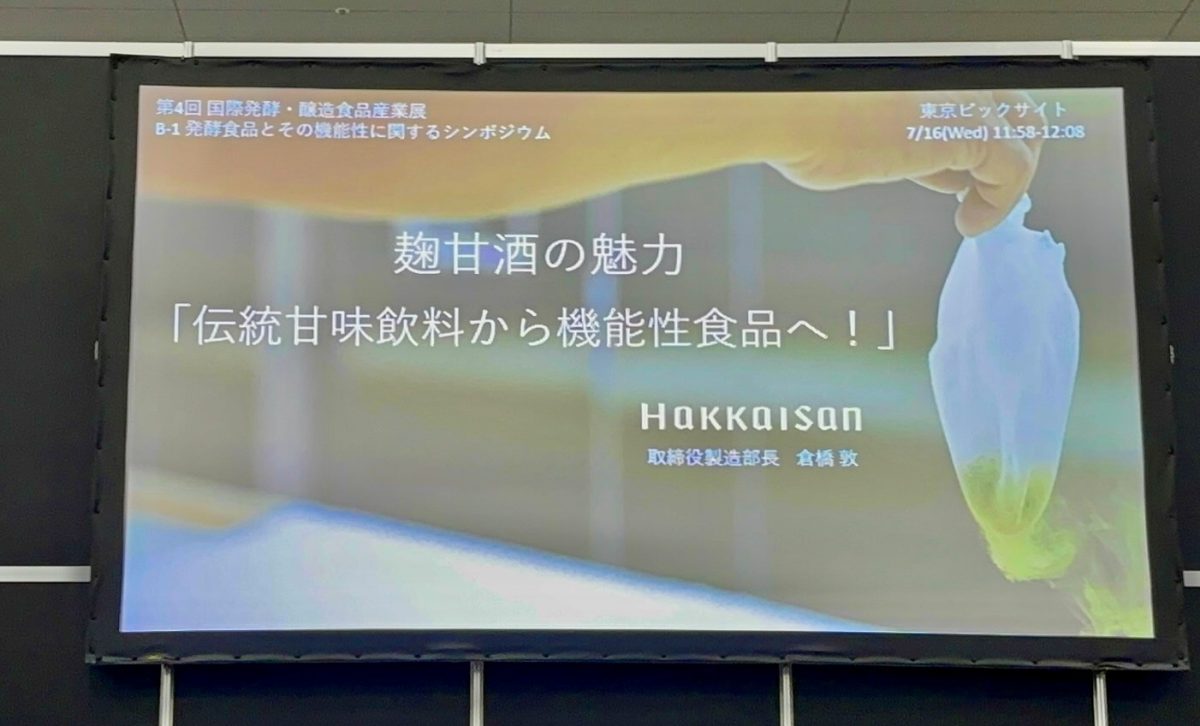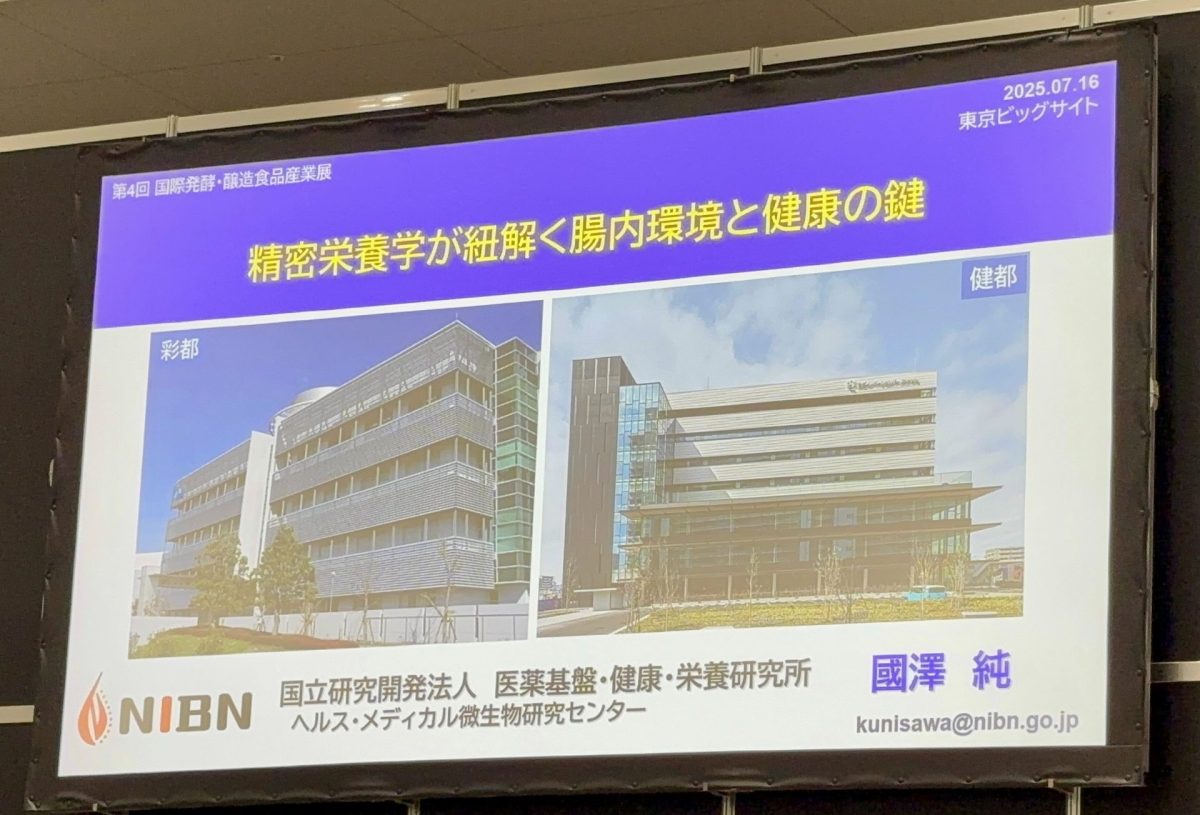
2025年7月16日(水)~18日(金)、東京ビッグサイトにて「国際発酵・醸造食品産業展セミナー」が開催された。『国際発酵・醸造食品産業展』は、発酵・醸造に関わる食材、素材、研究機器、製造設備、検査機器、パッケージ製品などを一堂に集めた日本唯一の専門展示会で、2013年に「和食」、2024年に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、以降、日本の発酵・醸造業界への関心は年々高まっている。ここでは国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所の國澤純氏による「精密栄養学が紐解く腸内環境と健康の鍵」を取り上げる。
国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所 國澤純氏
腸内細菌叢のあり方が私たちの健康を左右する重要な要素であることは間違いない。免疫や疾患だけでなく、脳や睡眠の状態、近年注目されている「痩せ菌」や「美肌菌」といった腸内細菌は、私たちの体質や見た目にも影響を与える。そもそも腸を健康に保つには蠕動運動が正常でなければならない。蠕動運動=快便だけでない。腸の中を特殊な機械で観察すると小さな点が動いているのが見えるが、これは免疫細胞で誰の体の中でも免疫細胞は蠕動運動と連動し絶えず動き回っている。さらに免疫細胞は腸内だけでなく、全身を動き回る。腸内細菌を整えると健康になる、という話の答えは「動く免疫細胞」にあるといってもよい。つまり腸活において重要なのは、腸が消化管として働き、そして免疫が働くことだ。ただし、免疫は高すぎず低すぎず整った状態で保ちたい。腸内細菌が良い働きをして、短鎖脂肪酸などをしっかり作っている状態が「良い腸内細菌」に当たるだろう、と國澤氏。
そこで登場するのが精密栄養学だ。「あなたはこれを食べた時に効くのはこうだからです。逆に、効かない場合はこうだからです」と科学的に説明し、その人に合った食事を提案できるようにする。これが英語では「Precision Nutrition」、日本語で「精密栄養学」という新しい学問であり、今注目されている。食物繊維は「食べ物の残りかす、便のかさ増しだけだろう」と思われていたが、腸管で油や糖を絡め取って私たちの体への吸収を抑える働きがあることが知られている。そして最近の研究から、さらなる働きがあることが分かってきた。キーワードは「短鎖脂肪酸」と「菌のリレー」だ。食物繊維は私たちの酵素では分解できないが、腸内細菌、特に善玉菌が分解できる。そして、分解した結果作られるのが短鎖脂肪酸だ。この短鎖脂肪酸は、腸のエネルギー源となる。腸が蠕動運動をするためにはエネルギーが必要だが、そのエネルギーの一つとして短鎖脂肪酸が働いている。さらに、免疫にも働き、特に免疫の暴走を抑える働きがあるため、免疫バランスを整える上で非常に重要な役割を果たす。加えて、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす働きもあるため、腸活を考える上で非常に良い働きをしてくれる。つまり、食物繊維をしっかり摂り、短鎖脂肪酸を作ることが、一つの腸活の目標になるだろう。中でも発酵性食物繊維に注目してほしい。食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられてきたが、最近は「短鎖脂肪酸になるかどうか」が重要で、短鎖脂肪酸になりやすい食物繊維を発酵性食物繊維と呼ぶ。発酵性食物繊維はごぼう、もち麦、押し麦、バナナ、長芋などに多く含まれるが、最近は製品パッケージに「発酵性食物繊維」と記載されているものもある。
ただし、発酵性食物繊維を摂れば腸内細菌が勝手に短鎖脂肪酸を作ってくれるほど、話は簡単ではない。食物繊維から酪酸を作るまでには大きく3つのステップがある。第一ステップが納豆菌や糖化菌と呼ばれる菌が、食物繊維を分解して糖を作り、第二ステップで乳酸菌やヨーグルトに含まれる菌が、糖を材料にして乳酸や酢酸を作る。そして第三ステップでようやくプロピオン酸菌や酪酸菌といった菌が、乳酸や酢酸を材料にして、プロピオン酸や酪酸を作る。酪酸は非常に注目されているが、酪酸を作る酪酸菌が欠かせない。実はこの酪酸菌はビタミンB1を自分で作ることができない。ビタミンB1は私たち人間も食事から摂らなければならない栄養素だが、多くの腸内細菌は自分でビタミンB1を作ることができる。しかし、酪酸を作る菌の多くは自分でビタミンB1を作れないため、外部からビタミンB1を供給する必要があるのだ。実際にマウスをビタミンB1が入っていない餌で飼育すると、酪酸を作る菌が減少し、酪酸が作られなくなる。よって、まず酪酸菌を増やすためには、ビタミンB1をしっかり摂ることが重要だ。また、ビフィズス菌が少なかったら、第二ステップがうまく行かない。酢酸が作られないと、いくらビタミンB1をしっかり摂り酪酸菌がいたとしても、酪酸菌はその材料となる酢酸がないため、酪酸が作れないのだ。代わりに何が起こるかというと、糖だけがどんどん作られてしまい、もしかしたら太ってしまうかもしれない、という状況に陥る。
「菌のリレー」を考えると、第一、第二、第三のステップが連動して動いていることが重要だ。腸内細菌の状況を見ることで「あなたはビタミンB1を摂るべき」「あなたはビタミンB1に食物繊維とビフィズス菌を摂るべき」といった形で提案できる。これが精密栄養学の一つの事例だ。当然食事には多様性があった方が良い。特定の菌だけが過剰に存在する状態は「ディスバイオーシス」と呼ばれ、例えそれが善玉菌であっても、菌のリレーでできることは限られるため、様々な病気の原因になるのではないかと言われているのだ。
「痩せ菌」ブラウティア菌の発見
現在は日本各地の様々な人のデータを取得し、健康との関わりを調べている。そこで見つかったのが「痩せ菌」ことブラウティア菌だ。世の中のニーズとしては「太りにくくする菌」の方が高い。実はヨーロッパでは、アッカーマンシア菌が体重コントロール菌として、すでに食品として開発しており、ネットでもサプリメントが販売されている。私たち日本人は世界的に見て肥満の少ない人種であるが、予想に反して、日本人でアッカーマンシア菌を持っている人は非常に少なく10人に1人いるかいないかだ。しかし日本人の肥満ではない人や糖尿病ではない人は特にブラウティア菌が目立つことが分かった。この菌は、日本人が非常に多く持っている。1%以上ブラウティア菌を持つ人は、日本人の約9割に及ぶ。日本人には馴染みのある菌であるが、「この菌は本当に体重コントロールに関わるのか?」という疑問から肥満マウスに飲ませてみたところ、体重の増加が緩やかになり、糖尿病も軽減された。つまり、ブラウティア菌は太りにくくする菌として、体重コントロールに寄与する可能性が期待される。さらにブラウティア菌はアルギニン、シトルリン、オルニチン、短鎖脂肪酸である酢酸といった物質を作っていることが分かった。第二ステップでビフィズス菌が酢酸を作ると言ったが、実はビフィズス菌だけでなく、ビフィズス菌が少なくてもブラウティア菌がいれば、ブラウティア菌が代わりに酢酸を作ってくれる。つまり、このブラウティア菌は、日本人で特に多く、健康で太っていない人に多い菌であり、オルニチンなど代謝促進物質を作りながら、短鎖脂肪酸である酢酸などを作り腸内環境を整え、さらには、自分自身が死んだら食物繊維と同じような働きをして、他の善玉菌の餌にもなるという、非常に良い働きをしている。
ブラウティア菌の測定と健康サイクル
現在、私たちはブラウティア菌を増やすにはどんなものを食べたら良いのか、あるいは、その菌を薬や食品としてそのまま利用できないか、といった研究を進めている。また、「自分の腸の中にブラウティア菌がどれくらい存在しているか」も気になるだろう。ブラウティア菌がどれくらい存在すれば、糖尿病や肥満のリスクが下がるかというデータを見ると、1%ではまだ不十分で糖尿病や肥満のリスクがある。しかし、これが6%程度になると、肥満や糖尿病のリスクはかなり下がる。とりあえず6%〜15%くらいまでを目指すのが良いと考えられる。
私たちが提唱する「腸活」が、個々に合わせた「精密栄養学」という形で、戦略的に実行できるようになるだろう。そして、健康のサイクルを作ることができる。まず、腸内細菌の全体像を知ることが必要だが、それが分かれば、何を増やし、何を減らしたら良いのかが分かる。そうすると、それに合わせた食事の提案が可能になるのだ。例えばビフィズス菌だけ、あるいはブラウティア菌だけ、といった特定の菌の動向を知りたい場合に、それだけを調べることができる。そうすれば、それほどお金も時間もかからずに済む。そして、目的の菌が増えてきたら、また再度調べて確認すれば良いのだ。このサイクルは、おそらく何回も回す必要はなく、数回回せばきれいなバランスになっていくのではないかと考えている。 これらの研究は、様々な先生方や研究機関からのご支援、そして大阪にある私たちの研究室のメンバー、さらには社会実装には私たちだけではできないという認識のもと、様々な方々に参加していただいている。もし興味があればお声がけいただきたいとまとめた。