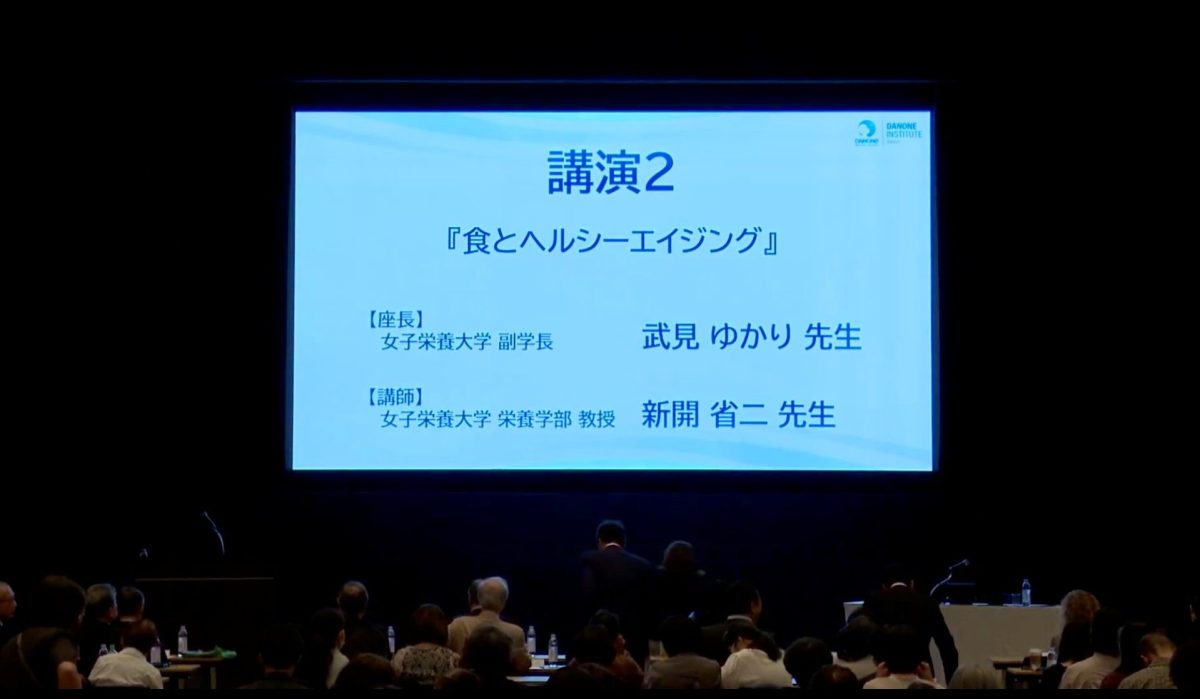
2025年10月4日(土)、東京国際フォーラムにて、そして10月20日よりオンラインで「第27回 ダノン健康栄養学フォーラム」が開催された。今回のフォーラムでは「ヘルシーエイジング」をテーマに四人の専門家が講演を行なった。ここでは女子栄養大学 栄養学部 教授 新開省三氏の講演を取り上げる。
女子栄養大学 栄養学部 教授 新開省三
新開氏は本講演で、日本の抱える複雑な世代ごとの栄養問題と、食事が健康寿命に及ぼす影響、そしてその解決策について、具体的なデータに基づいて解説。
世代間で大きく異なる日本の栄養問題の現状
日本の栄養問題は世代によってその様相を大きく変えており、新開氏によると、まず子ども世代では、かつて問題視された小児肥満に加え、近年では一人親世帯の貧困などを背景に痩せの子どもが増加傾向にあるという、二極化の傾向が見られるという。次に若年層、特に若い女性の痩せの問題は深刻で、これは単なる個人の健康問題に留まらず、次世代への影響も非常に大きいため国も問題視し始めていることを指摘。また、高学歴者層においても、多忙さやストレスから食事がおろそかになっている現状があり、特に女性は労働と家庭の二重の負荷が食生活に悪影響を与えている可能性があるとした。そして中年世代では、男性のメタボリックシンドロームは依然として微増傾向が続いている。その一方で、若年層の痩せの傾向が続くことで、その層が40代に差しかかるにつれて女性のメタボは減少傾向にあるという。高齢者の世代では、全体的に低栄養傾向や痩せが最も大きな問題だ、と指摘。特に後期高齢者や80歳以上では、食環境の問題(買い物や調理の困難さ、食欲の低下など)が生活機能の維持を脅かす要因として非常に大きい。新開氏は、これらの世代間の多様な問題を丁寧に解決するためのアプローチが必要で、通り一遍の政策ではヘルシーエイジングの達成は難しいと警鐘を鳴らす。
死亡リスクから見る健康的な体格
健康を考える上での究極のアウトカムは死亡リスクである、と新開氏。そこでBMIと死亡リスクの関係について、国立がんセンターの研究者らによる中高年の大規模コホート研究(男性16万人、女性19万人を10年以上追跡)のデータを提示。その結果によれば、BMIが21から27の範囲では、死亡リスクに統計的な差がないことが明らかになっていると解説。日本の肥満学会の基準(25以上で肥満)とは異なるものの、大規模データから見ると健康的な体格にはかなり幅があるのが現状だ。肥満(BMIが高いこと)は主に中年世代の課題であるが、痩せ(BMIが低いこと)が問題になるのは高齢期であり、高齢者においては痩せのリスクは肥満に比べて異常に大きい。また、健康寿命の土台となる骨量と筋肉量は、20代から40代前半をピークに減少していく。高齢期に骨折やサルコペニアのリスクを低く抑えるためには、このピーク時の量を高めること、すなわち若いうちから骨・筋肉の健康に留意しておくことが、長い目で見て非常に重要である、と強調。
いずれにせよ、ヘルシーエイジングに向けた健康上の指標は、中年期と高齢期で大きく異なると言える。中年期がメタボリックシンドロームや生活習慣病の予防に主眼があるのに対し、高齢期は個別の疾患よりも心身機能や社会機能を含む包括的な生活機能の低下予防、すなわち健康寿命の維持・延伸が最大の目標となる。特に高齢期では、地域疫学研究のデータから、高血圧などの疾病要因だけでなく、握力や歩行速度といった身体機能、そして血中アルブミンなどの栄養状態を示す加齢関連要因が、介護認定(健康寿命の喪失)のリスクに非常に強く影響することが示されている。注目すべきデータとして、高齢期では脂質異常症やメタボリックシンドロームの有無が必ずしも健康寿命の喪失リスクと関連しないことが示された、という点を指摘。高齢期においてはこれらの指標が疾病マーカーというよりも低栄養のマーカーとして作用する可能性を示唆しているのではないか、と新開氏。一方、フレイル(虚弱)やフレイル予備群は、その後の生活機能低下を強く予測する。このことから、高齢期の健康維持には、疾患管理に加え、加齢による機能低下を包括的に捉える老年症候群への対策、すなわち生活機能の低下予防が最重要課題となることが裏付けられるのでは、と解説。
高齢期の健康を支える「食」の3つの柱
高齢期の健やかな老化に必要なのは「栄養」「体力」「社会参加」の3つの要素であり、これらの要素が揃う人ほど、その後の自立喪失リスクが低いことが、大規模な追跡調査によって裏付けられている、と新開氏。特に食の分野においては、以下の3点が、ヘルシーエイジングを支える柱として重要である。まず「多様食(多品種の摂取)による栄養密度の向上」だ。研究で開発された「食品摂取の多様性スコア(DVS)」は、肉、魚、卵、大豆、牛乳、野菜など10種類の食品群を「ほぼ毎日食べる」かについて評価する簡便な指標であるが、DVSが高い食事は、一定のエネルギー摂取量の中でたんぱく質や微量栄養素、食物繊維の摂取量が増加し、栄養密度が高いという特徴がある。DVSが高い高齢者は、身体機能や筋肉量が良好で、要介護・認知症の発生リスクが低く、精神的健康度も良いことが分かっている。さらに、DVSを改善するための介入試験(3ヶ月間)を行った結果、握力や下肢筋力(誤解椅子の立ち座り時間)が統計的に有意に向上することが確認された。この事実は、食事の多様性を高めることが、直接的にフレイル予防につながる身体機能の改善効果をもたらす可能性を示している。次に「美味しく食べるための口腔の健康」が重要で、美味しく十分な栄養を摂取するために、口腔の健康、すなわち咀嚼機能が欠かせない、と指摘。一般高齢者では咀嚼機能が不良と判定される方が約6割に上り、咀嚼機能が低下すると肉類や魚介類の摂取が減少し、低栄養の割合が約2倍に増加する。新開氏は、歯周病などで歯が抜けても、適切な義歯(入れ歯)を使用し、機能歯を維持することで、20本以上の歯を持つ人と同等の健康寿命を維持できることを示し、かかりつけ歯科医による口腔ケアと義歯の調整の重要性を強調した。そして3つ目が「楽しく食べる(共食)による精神的健康の維持」だ。高齢者では一人暮らしの増加に伴い、個食(3食すべてを一人で食べる)が基本となりつつある。地域研究のデータは、同居人の有無にかかわらず、3食を一人で食べる人は、そうでない人に比べてフレイル出現リスクが約2倍、精神的健康度が低いという結果を提示している。これは、食事が単なる栄養補給ではなく「共食」することで精神的健康(ウェルビーイング)の維持に非常に重要な役割を果たす独立した要因であることを示唆している。
食の力を活用した地域社会への提言 新開氏はこれらの知見を踏まえ、今後は地域社会において「食事を囲んで楽しく美味しく食べる機会を意識的に作る」必要があると提言する。自身の所属する大学では、学生が被災地を訪問し、地域住民と一緒に料理を作る「共食を通じた世代間交流」を実践してきた。当初は交流に消極的だった高齢者も、「美味しいものが食べられる」「学生が来てくれる」という食の力によって集まり、交流を深めている。この活動は、栄養バランス改善の啓発だけでなく、世代間交流や社会参加を促し、地域の健康づくりとコミュニティの再構築に大きく貢献しているという。新開氏は、食事とは単に栄養を摂取するだけでなく「どういうシチュエーションで、誰と、どういう交流をしながら取るのか」という位置づけを大事にすべきであると結論付け、ヘルシーエイジング達成のための食の新たな役割になるとまとめた。








