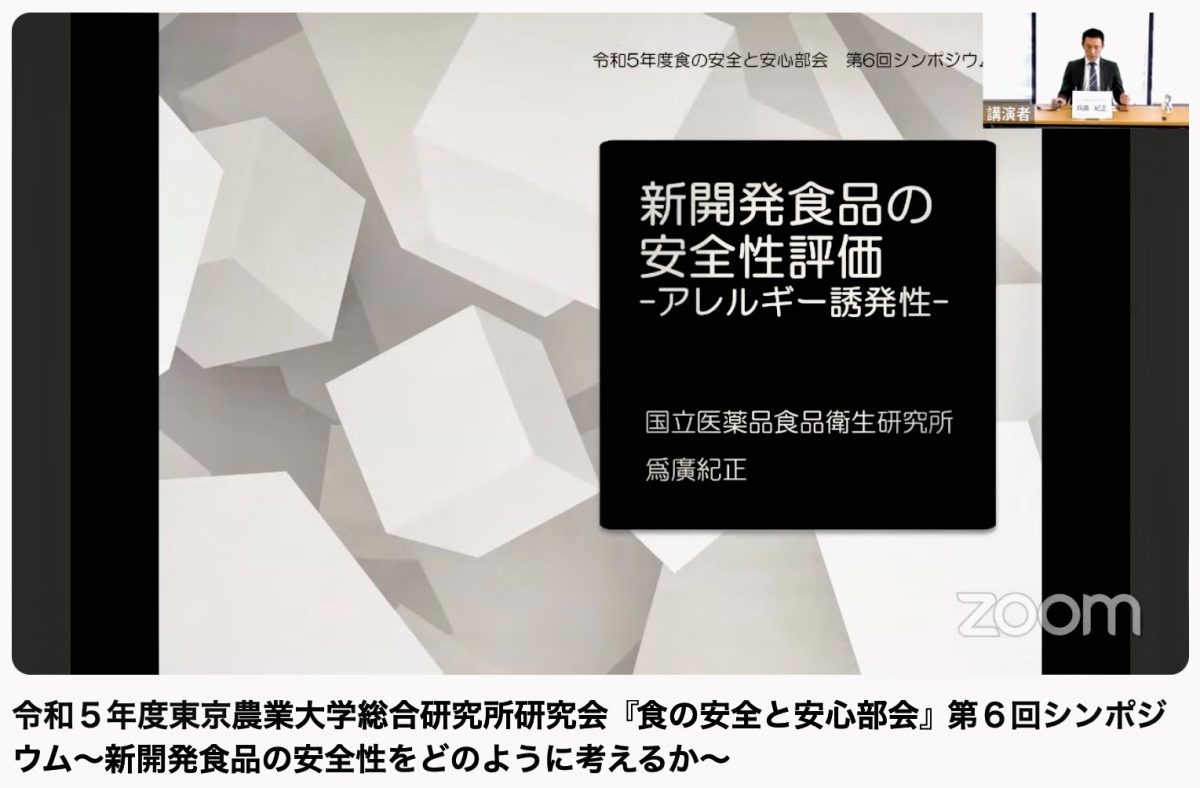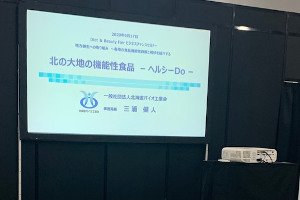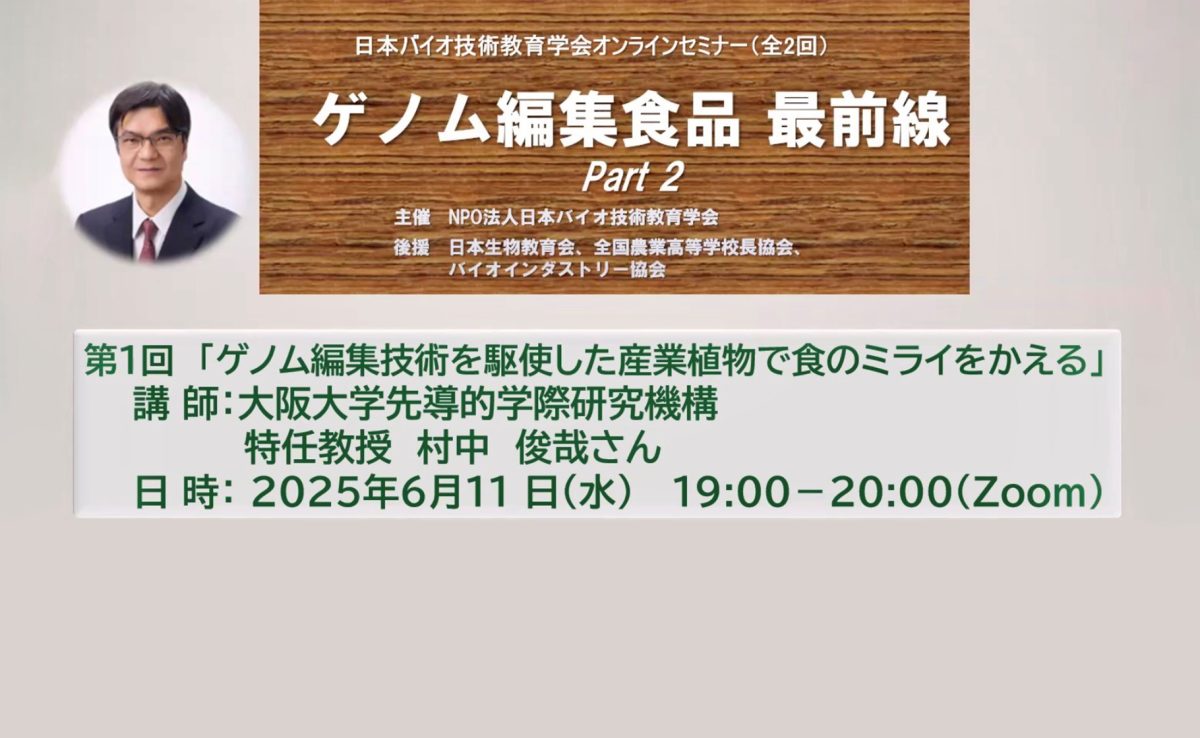
2025年6月11日(水)、日本バイオ技術教育学オンラインセミナー2025「ゲノム編集技術を駆使した産業植物で食の未来を変える」が開催された。第一回目は「毒のできにくいジャガイモ」を産業植物という新たなカテゴリーで生み出す研究をしている大阪大学先導的学際研究機構 特任教授 村中 俊哉氏の講演を取り上げる。
大阪大学先導的学際研究機構 特任教授 村中 俊哉
「ゲノム編集」という言葉は広まりつつあるが「産業植物」という表現に馴染みのない人が多い。本講演で、この言葉の意味と、その背景にある思いをお伝えできれば、と村中氏は話す。村中氏は今年3月をもって大阪大学工学研究科を定年退職し、現在は「産業植物イニシアティブ(SIPA Initiative)」に所属している。ここでは、研究開発だけでなく、産業植物という概念に基づいた社会実装を目的としたプロジェクトに取り組んでいる。講演では特に「ジャガイモ」に焦点を当てて話が進められた。
意外に思われる人が多いが「ジャガイモはサツマイモよりもトマトに近い」という。ジャガイモとトマトはともにナス科ソラヌム属に分類され、人間で言うところの同じ「属」に当たる。両者は南米原産であり、原種は小さく、野生のトマトは小さくて苦く、毒を持ち、発芽も不揃いだった。そこから人為的な品種改良を経て、大きく甘く、毒がなく、食用に適した現在のトマトが生まれた。一方、ジャガイモは、今でも「毒」を完全に避けられない。芽が出たり、緑化するとソラニンやチャコニンといった毒素が発生する。最近だと2019年に兵庫県宝塚市の小学校で児童が栽培したジャガイモを食べて中毒症状を起こす事故もあった。現在、主要作物(稲、小麦、大麦など)の中で、毒性を気にしなければならないのはジャガイモだけになっている。
この毒性物質は「ステロイドグリコアルカロイド(SGA)」と呼ばれ、ソラニン、チャコニンなどが該当する。トマトにも未熟な果実にトマチンというSGAが含まれるが、熟すと高機能成分に変わるため問題にはならない。SGAは植物内で複雑な代謝反応により生成される。ある酵素が物質AをBに変え、BをCに変えるといった連鎖の中で、副産物として毒性物質が生成される。この中で毒の生成に関わる特定の酵素が判明すれば、その酵素を作る遺伝子を破壊すれば毒を抑えられる、という論理が成り立つ、と村中氏は解説。実際、こうしたことを可能にしたのがゲノム編集技術である。遺伝子配列を狙って改変することで、目的の性質だけを変えられるのだ。DNAは二重らせん構造で、紫外線などの刺激により切断されることがある。通常は細胞がこれを修復するが、修復過程でミスが起こる確率は10万〜100万回に1回程度あり、これが自然界で起こるようになるのが突然変異だ、と説明。
例えば、稲の「穂が落ちやすいかどうか」は、ATTTCAという配列の中で1文字が変わるだけで変化する。このような変異を経験的に選抜して利用してきたのが従来の品種改良であり、これを狙って起こせるようにしたのが、現代のゲノム編集技術。事例として自家受粉しなくても実がなるナスの例を紹介。遺伝子の一部を欠失することで、自家受粉を必要とせずに実が育つようになる。このような性質を自然の偶然ではなく、意図的に作り出すことが可能になったのがゲノム編集の基礎的な原理であり、品種改良の新たなステージである、と話す。
ではこの技術を使って実際にジャガイモの毒を取り除くことができるのか。鍵となるのが「SSR2」という遺伝子である。SSR2は、SGA(毒性物質)の生成過程で重要な役割を果たしており、これを破壊すれば毒のないジャガイモが実現する可能性がある。実際に、村中氏の研究グループは、SSR2遺伝子をゲノム編集で破壊することに成功した。その結果、ソラニンやチャコニンの含有量が大幅に減ったジャガイモの個体を得ることができた。この研究は、当初は「サシー」という品種で行われ、後に「サヤカ」というサラダ向け品種のジャガイモでも成功しているという。ただし、当時のゲノム編集技術は現在主流となっている「CRISPR-Cas9」がまだ十分に利用できる段階になかったため「TALEN」という別のゲノム編集技術を用いて研究を進めたそうだ。
ゲノム編集作物の取り扱いについては「カルタヘナ法」によって規制の有無が決まる。外来遺伝子が残っていなければ、規制の対象外となるというのが日本のルールであるため、このルールに基づき、村中氏らが開発したゲノム編集ジャガイモも規制外と判断された。
2021年には文部科学省に届け出を行い、理化学研究所と共同で、毒性成分の少ないジャガイモの野外試験を開始した。初年度は条件が悪く成果が限定的だったが、翌年には畑作適地での栽培により、十分な収量が得られた。ただし「サヤカ」品種では収量がやや低下する傾向があった。この影響がSSR2遺伝子の破壊によるものかどうかは、現在も検証中であるという。
次の課題は「芽が出ないジャガイモ」の開発であるという。ジャガイモは保存中に発芽しやすく、それによって毒が発生し、商品価値が落ちる。2016年にはジャガイモの主産地である北海道がゲリラ豪雨で被害を受け、翌年には全国的なポテトチップス不足に繋がった。このような需給不安定を防ぐには、芽が出ない品種の開発が必要なのだ。村中氏らの研究では、SSR2の発現をRNA干渉により、毒が減るだけでなく芽も出なくなるという性質を確認した。この状態で土に植えれば正常に発芽するが、保存中は芽が出ず、必要な時だけ発芽するという、極めて都合のよい形質である。この性質をRNA干渉ではなく、ゲノム編集によって再現する研究が2019年から2023年にかけて進められ「保存中に芽が出ず、加工に適したバレイショ(ジャガイモ)」の開発が進行した。
現時点で「毒が少なく芽が出ない」という成果が得られ、野生型と比較して10ヶ月経過しても発芽しないことが確認されている。今後は北海道での本格的な栽培試験が必要な段階だという。
このような技術開発を包括する概念が「産業植物」だ。従来、農作物や薬用植物は別々の研究対象とされてきたが、それらを横断的にとらえるために「産業植物」という新たな言葉を提唱している、と話す。植物は人類の健康と地球環境の持続可能性に大きな貢献ができる。そして産業植物は、フードロス削減や環境負荷の低減に直結することを目的としているという。2024年には大阪大学公認のクラウドファンディングを実施し「芽掻き不要の丸ごと食べられるジャガイモ」や「無駄ゼロの培養革命」などのプロジェクトを展開することで、多くの支援を得られた。 現在は、ゲノム編集技術を活用して、毒が少なく芽が出ないだけでなく、病虫害に強いバレイショの開発、小麦やトマト、大根などへの応用研究も進めているという。将来的には、ゲノム編集の力で「産業植物」という新たなカテゴリーを社会実装していくのが目標だと話した。