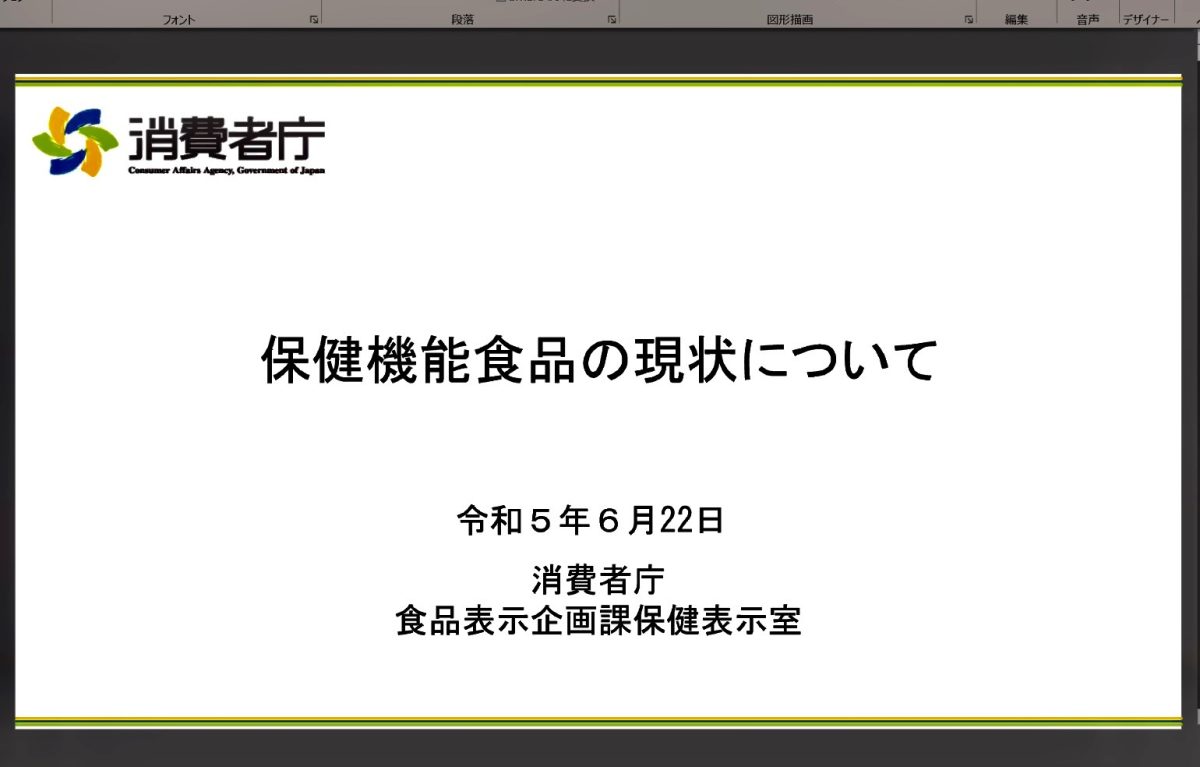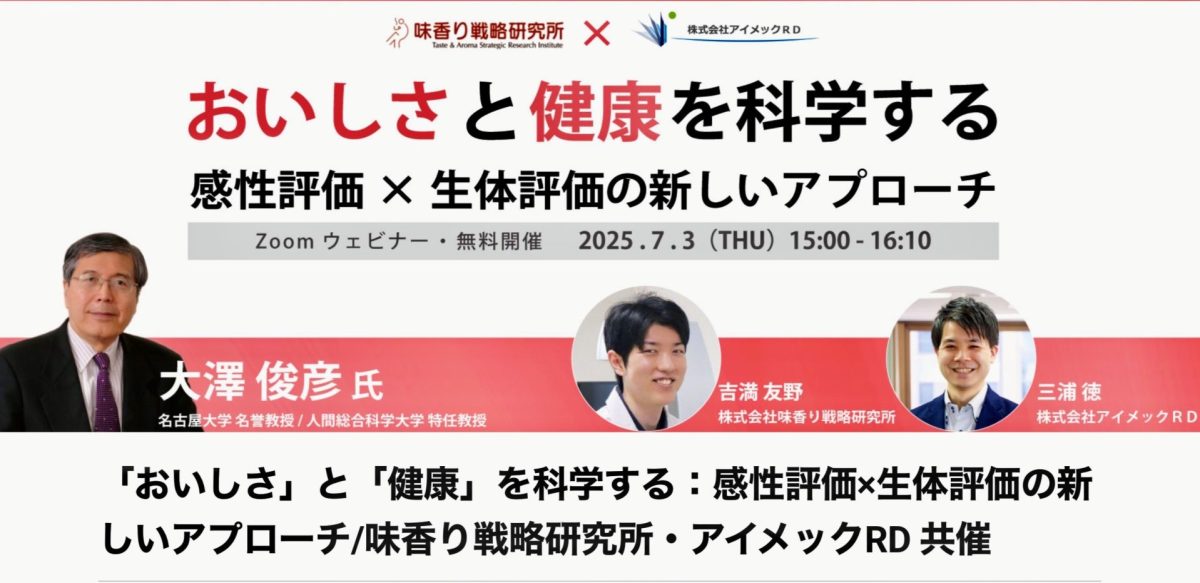
2025年7月3日(木)、オンラインにて「おいしさ」と「健康」を科学する 感性評価×生体評価の新しいアプローチ」が開催された。ここでは名古屋大学名誉教授 人間総合科学大学客員教授 大澤 俊彦氏による「味と香りが導く健康長寿:食品機能科学の最前線」を取り上げる。
名古屋大学名誉教授 人間総合科学大学客員教授 大澤 俊彦
フードファクターという言葉は、1990年にアメリカでスタートした「デザイナーフーズプログラム」に遡る。ここで初めて約40種類の野菜や果物、ハーブ、スパイスに含まれる「ファイトケミカル」が、がん予防において重要な役割を果たすということを示したピラミッド型の図が作成された。これがいわゆる「デザイナーフーズ・ピラミッド」と呼ばれるものだ。大澤氏はこれが「がん予防」にとどまらない、食の機能性全体に関わる重要な視点だと捉えている。そこで1995年に浜松で開催された「フードファクター国際会議」で「フードファクター」という言葉を公式に提唱し、その後「日本フードファクター学会」を設立。大澤氏が初代理事長を務めた。
フードファクターには「感性」や「おいしさ」「香り」などの「第二次機能」、そして「第三次機能」が含まれる。アメリカのデザイナーフーズ計画には約40種類の野菜が対象となったが、大澤氏はこれを日本型に応用しようと考え、例えば、ゴボウや春菊といったキク科植物、シイタケやキクラゲなどのキノコ類、海藻類など、日本の食文化に根ざした食材を取り入れた「日本型デザイナーフーズ」の構築を試みた。その中でも大澤氏が注目したのが「チョコレート」だ。すでに注目されていたココアに加え、チョコレートは苦味と香りが特徴的だ。そこで「第三次機能」の観点からのチョコレートの可能性、中でも「認知症予防」に関するものに注目したという。アルツハイマー病(AD)の脳には病変部が確認され、軽度認知障害のレベルでは健常者とADの中間の状態が確認できる。軽度の段階でチョコレートの第三次機能を活用し、うまく対応できれば、認知症の進行を予防し得る可能性がある、と大澤氏。
同時に大澤氏らはバイオマーカーの開発に取り組み、LC-MS(液体クロマトグラフィー・質量分析)を用いて、小規模な介入試験や動物実験を通じて発酵素材に注目した研究も行っている。例えば、発酵アスタキサンチン、発酵レモンピール、発酵ゴマリグナンなどだ。これらの素材を活用し、香りや味と機能性の関連を見出すことで、単なる疾病予防にとどまらず、「おいしさ」と健康の融合を目指したいと考えている、と話す。
食品機能として見逃せないのが発酵食品の効能である。そもそも発酵食品は嗜好性が向上するという特徴がある。さらに、大澤氏らの研究では、発酵によって抗酸化性が高まり、吸収率などの面でも優れることが明らかになっている。これまでに、テンペ、八丁味噌、レモン果皮の発酵物などの共同研究を行っており、例えばウコンの黄色色素を発酵により変化させて得られる「テトラヒドロクルクミン」、海洋藻類の赤色色素「アスタキサンチン」などもすべて発酵を通じて機能性が高まることがわかっている。これらの素材を将来的には「味・香り」を含めた新たな素材研究・食品開発へと展開していきたい、と話す。
実例としてゴマリグナンの代表成分である「セサミン」について報告。ゴマ油を絞った残渣から抽出される成分セサミノール配糖体についても、発酵によってセサミンやセサミノールといった新たな機能性成分が得られることを確認している。ターメリック(ウコン)に含まれる黄色色素は、カレー粉の主成分であるが、腸内で吸収される段階で無色・無臭となるこの成分が、実は強力な抗酸化作用を持つことを明らかにし、これは酵母や乳酸菌、大腸菌などの働きによって得られるものであることも解明できているという。最近では、発酵によって新たに生成される生理活性物質に関する論文も発表し、これを基に香りや味と機能性の融合を目指す研究が進んでいる。
同じく野菜や果物にも注目が集まる。特にわさびやクレソン、ブロッコリーなどのアブラナ科植物を中心に研究を行ってきたが、中でもクレソンは、その抗酸化成分の高さが注目され、現在多くの研究が進められている。果物ではバナナの研究を通じて運動機能の改善効果を見出してきたが、パパイア、アボカド、パイナップルにも解毒酵素を活性化させる機能が認められ、注目を集めている。
さて、大澤氏が30年近く研究してきたカカオポリフェノールは「高カカオチョコレート」として商品化されており「蒲郡スタディ」では、1日25gの摂取により血圧を下げ、動脈硬化のリスクを低減することを約400名の対象者を用いた大規模な研究で示された。この高カカオチョコレートの摂取は、BMIにも影響を与えず、安全性も確保されている。さらに、高カカオチョコレートの摂取によって心理的ストレスが軽減されることが示され、アンケート調査においても精神的健康度の向上が確認されている。その作用メカニズムとして注目されたのがBDNF(脳由来神経栄養因子)だ。この因子はニューロンの生成を促進するが加齢とともに減少する。大澤氏らの研究では、4週間のチョコレート摂取によりBDNFが有意に増加することが示された。さらに、他の機能性成分や運動習慣と組み合わせることで、BDNFのさらなる増加が期待され、認知症予防における新たな可能性を示唆している。
そしてフードペアリングの概念についても知ってほしいと話す。例えば72%カカオの高ポリフェノールチョコレートは苦味が強く、同時に香り成分を多く含んでいるが、86%や95%といった高濃度チョコレートでは、香りはやや抑えられた一方で苦味が強くなる傾向がある。このようなフードファクターの組み合わせによる「フードペアリング」が、新たな機能性をもたらす可能性に注目している、と説明。特に香りの成分に関しては、硫黄系、アミン系、アルデヒド系、エステル系など複数の化合物が存在し、それらが人の嗅覚に与える影響が重要な研究対象となっている。その一環として、チョコレートと風味の共通点を持つごぼうの焙煎成分に着目。実際、ごぼうを使ったチョコレートは商品化されている。現在は味と香りの観点からのアプローチであるが、今後は健康機能の面からも研究・評価すべき、と大澤氏。例えばパパイア、キウイ、バナナといった果物の機能性に注目し、これらの食材とチョコレートとの相性から生まれる新たな健康機能性(ペアリング)が今後の研究テーマとして重要だ。ギャバ入りチョコレートはすでに江崎グリコ(株)から商品化されているが、それは単なる栄養補給を目的としたものであり、大澤氏らが目指すフードペアリングによる機能性の強化とは異なるアプローチだ。大澤氏らはギャバを含むチョコレートに加えて、バナナ、パパイア、パイナップルなどの果物を組み合わせることで、味覚的な満足度と機能性の両立が図れるのではないか、と説明。
そもそもギャバは果物や野菜に多く含まれ、発芽や発酵によってその含有量が増加する成分だ。また機能性表示食品において、ギャバは届け出数が最も多い成分の一つである。ギャバは血圧低下効果のほかに、ストレス軽減効果にも注目が集まっているが、ストレス軽減のためには一定量以上のギャバ摂取が必要で、その点が課題である。しかしギャバに他の食品成分を組み合わせることで、必要量を抑えながら効果を高められる可能性がある。唾液中にはクロモグラニンAというタンパク質が含まれるが、これは特に不安時に唾液中に分泌される指標物質であり交感・副交感神経のバランスを測る生理指標の一つとされる。そして、ギャバの摂取によりクロモグラニンAの濃度が有意に減少し、交感神経系の過剰な活性が抑えられることは示されている。つまり、ギャバは主に交感神経系の抑制を通じて、ストレスを低減する効果を発揮している。一方、ギャバによる副交感神経系の活性化、すなわち安静状態や快適な睡眠の促進に対する効果については明確な結果が得られていない。今後は副交感神経を活性する機能性成分との組み合わせに、香り・味覚と連携させることで、より包括的な精神的健康の改善が目指されるべきである。 「フードファクターサイエンス」では、これまでに100種近い素材の研究に携わり、60件以上の特許を取得してきたが、多くの特許は未だ活用されておらず、実用化されていない。これらの知見や技術、ノウハウは十分に蓄積されているため、今後は皆様とともに新たな機能性食品の開発に取り組み、健康とおいしさを兼ね備えた次世代の食品を創出したい、と語った。

20221201_第2回-国際発酵・醸造食品産業展 新世代の機能性食品素材開への試み(株式会社アイメック)--1200x916.jpg)