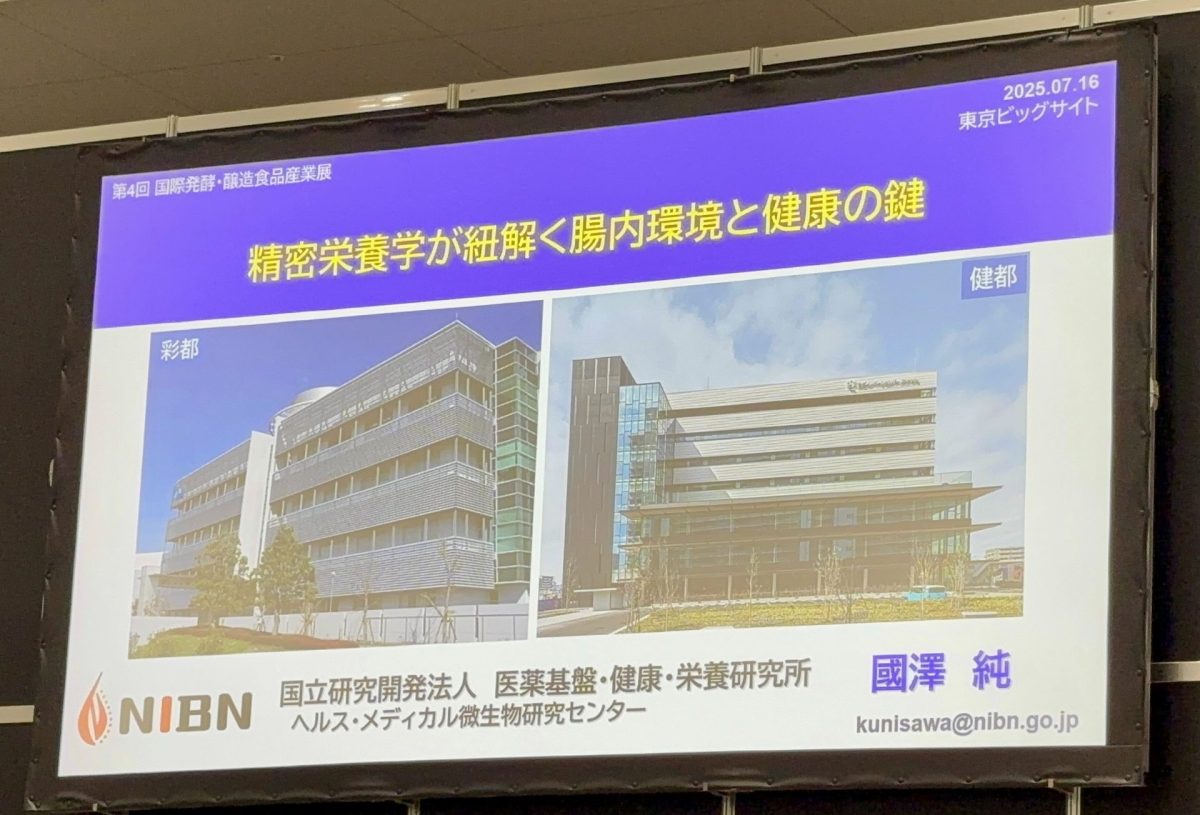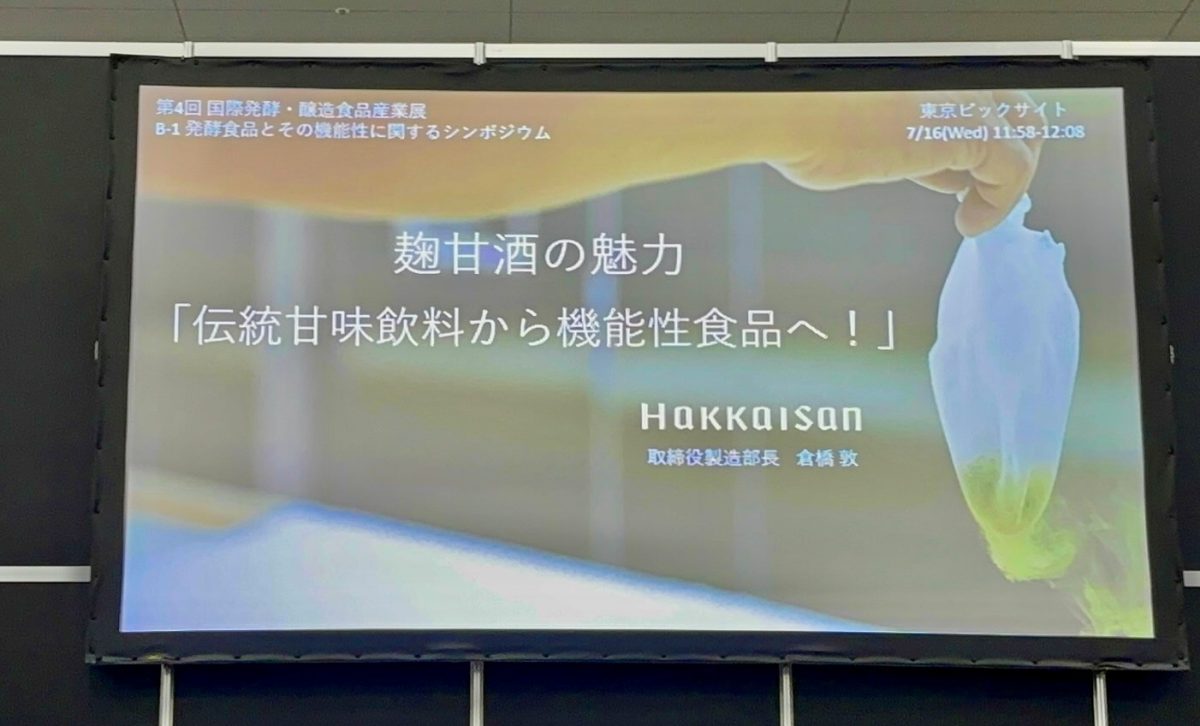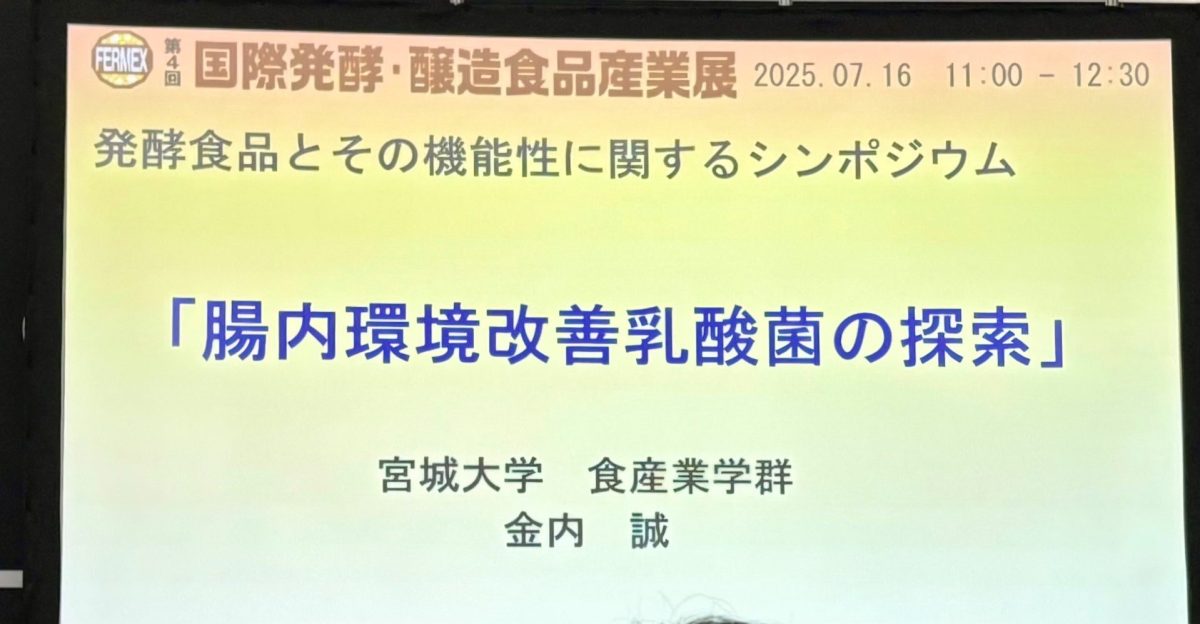
2025年7月16日(水)~18日(金)、東京ビッグサイトにて「国際発酵・醸造食品産業展セミナー」が開催された。『国際発酵・醸造食品産業展』は、発酵・醸造に関わる食材、素材、研究機器、製造設備、検査機器、パッケージ製品などを一堂に集めた日本唯一の専門展示会で、2013年に「和食」、2024年に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、以降、日本の発酵・醸造業界への関心は年々高まっている。ここでは「発酵食品とその機能性に関するシンポジウム」より、宮城大学教授 金内誠氏による基調講演「腸内環境改善乳酸菌の探索」を取り上げる。
宮城大学教授 金内誠氏
和食と発酵食品の注目度から腸内細菌研究へ
和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され、2024年12月には「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されることで、世界中から注目され続けている。日本では古来より発酵食品の需要が高く、例えば金内氏はユーキャンと共同で「発酵食品マイスター」という資格提供に関わっているが、現在1万人ほどのマイスターが誕生しているという。私たちが発酵食品を好むのはもちろん美味しいということが大前提であるが、近年は機能性への期待が高く、その機能性の多くは「腸内環境の改善効果」を狙っている。そこで金内氏らは「乳酸菌の腸内環境への作用」に着目。「腸内環境とはどのような状態が良く、どうすれば良くなるのか」ということを考えた結果「腸内で炎症が起きない」ことが良い環境の条件ではないかという結論に至った、と説明。
LPSと抗炎症作用に着目した研究
炎症が起きるとお腹が痛くなるということは漠然と理解されているが、「炎症」とは何なのか。食品中で増殖したものや腸内で増殖した菌が毒素を作り、その毒素によって炎症が起こることはわかっている。では炎症が起こる前段階で食い止めることはできないのか。そこで、金内氏らが着目したのがLPS(リポポリサッカライド、リポ多糖)という物質だ。LPSとは、グラム陰性菌(大腸菌に代表される菌)の外側にある物質であり、これに触れると粘膜が炎症する。このLPSを全てなくすことが良いわけでなく、ある程度残っている方が免疫系に緊張感が保たれるが、LPSによる炎症が重症化すると敗血症が起きることもあるため、良い物質とは言えない、と金内氏。
LPS不活性化物質の探索
このLPSを不活性化する物質が世の中にあるのか調べたところ、牛乳の中のタンパク質であるラクトフェリンという物質に辿り着く。ラクトフェリンは母乳に多く含まれるが、牛乳にも含まれる。しかし市販の牛乳は殺菌工程によって量が減少してしまい、ラクトフェリンがほとんど含まれない。乳に依存しないLPS不活性化物質がないか探索したところ、身近なところにあったと話す。
乳酸菌の健康機能とLPS不活性化作用
乳酸菌の健康機能については、腸内環境改善だけでなく、がん抑制、腫瘍抑制、歯周病抑制効果などが報告されている。そこで乳酸菌に直接LPS不活性化作用があれば良いのではないか、ラクトフェリンに代わる乳酸菌を見つけたい、と検討開始。米麹、味噌、チーズ、キムチ、ビール粕、ぬか漬けといった様々な発酵食品から乳酸菌を分離したところ、多様な種類の乳酸菌が得られ、これらの乳酸菌を用いて、炎症性物質であるLPSを不活性化できるかどうかを試してみた結果、ぬか漬けから分離した乳酸菌、特にY-23株という株が非常に良い結果を示した。このY-23株はメディオバクテリウム・フェカリスという菌種であることも判明。これはどのぬか漬けにも含まれる、珍しくない乳酸菌であるが、この菌がLPSを不活性化する能力が非常に強いことが分かった、と金内氏。さらに、LPS不活性化作用を持つ物質はY-23株の細胞壁に圧倒的に多いことも解明。細胞壁の部分だけを取り出して、次世代シーケンサーという装置を用いてタンパク質のアミノ酸配列を解析。その結果、ヒートショックプロテイン70(Hsp70)というタンパク質の一部であることが判明した、と説明した。このHsp70の一部とラクトフェリンを比較して、LPS不活性化能力を競わせてみたところ、Hsp70の一部の方がラクトフェリンよりも強いことが分かった。これは、ラクトフェリンに代わる、あるいはそれ以上の抗炎症作用を持つタンパク質が得られたことを意味する。
また、培養細胞を用いた実験の結果、乳酸菌由来のこのタンパク質は、高い抗炎症作用を持つことも確認できたという。我々の研究はここまでだったが、大学院生がY-23株由来の抗炎症タンパク質を経口摂取させたマウスの便中の菌叢解析を行ったところ善玉菌である腸内細菌が増える傾向があることが分かった。このことから、腸内環境は整ったと言える。ただし、これが健康に直結するかどうかは、まだ解析の余地があるとした。 以上の結果から、特別な乳酸菌でなくても身近な食品「ぬか漬け」に含まれる乳酸菌が、体の中に良い作用をもたらすことがわかった。もしこの乳酸菌(Y-23株由来の抗炎症タンパク質)が活用できるようになれば、腸内だけでなく、歯周病の治療にも応用できるのではないかと考えている、と金内氏。特に歯周病は歯茎の粘膜の劣化がLPSによって引き起こされることが分かっているため、この乳酸菌由来のタンパク質が有効に機能する可能性を秘めているのではないか、と報告した。