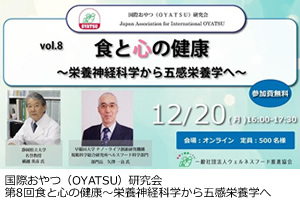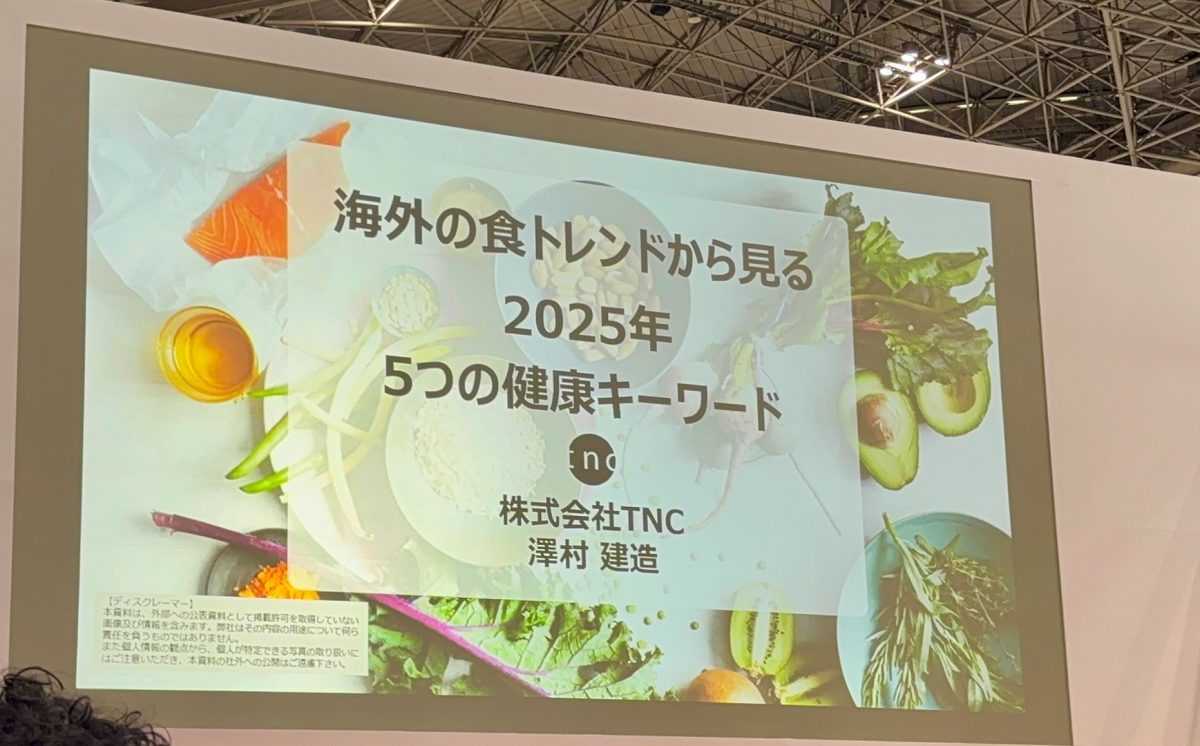
2025年2月26日(水)〜28日(金)、東京ビッグサイトにて「健康博覧会2025」が開催された。今年で43年目を迎える国内のヘルスケア展示会で最長の歴史を誇る「健康博覧会」。今年も健康食品やサプリメントに加え、ウェルネス、リカバリー、フェムテックだけでなくメンテックといった新たなカテゴリーも登場し、約500社の出展と約4万人の来場者で賑わいを見せた。ここでは出展社プレゼンテーションから「海外の食トレンドから見る、2025年の健康キーワード」を取り上げる。
(株)TNC ディレクター/グローバルフードアナリスト 澤村 建造
1. プラネットファースト(Planet First)
地球環境への配慮、環境負荷の低減、持続可能な地球環境といった、地球を考慮した食事の選択が、何よりも強く求められている。「プラントベースフード」「アニマルウェルフェア」「ブルーフード」などの概念が欧米を中心に広がりを見せており、エシカル(倫理的)な消費行動が注目されている。25年後の2050年には世界の食肉市場の35%が培養肉、25%が代替肉になると予測されており、現在のような肉食を続けることは難しいとされる。地球環境を考えると植物由来の食品に嗜好を移していく必要があり、そのような企業努力も求められる。他にも「食品廃棄物の削減」を目的としたアップサイクルフードの開発に注目が集まる。例えば、杏仁から作るミルクやヨーグルト、バナナの皮から作るシードルなどが登場。また「持続可能なパッケージ」が人気で、極力プラスチックを使用しない包装技術が求められる。このアップサイクルの観点から、「食とアパレル」など、異業種とのコラボレーションがトレンドになりつつあり、例えば、ワイン用の葡萄の廃棄物を利用したヴィーガンレザーで作ったアパレル用品などは世界各国で注目されている、と紹介。
2. フードイノベーション(Food Innovation)
最新技術を駆使し、食の可能性を広げる動きが進む。特にAI技術が食品開発に活用されるのがトレンドだ、と澤村氏。「フローズンミール」や「フリーズドライ技術」、「斬新なテイスト」などが最新技術によって続々と登場している。例えば「AIによるレシピ提案」は一般消費者レベルでも進んでいる。これまでは企業が開発チームを抱えて、新商品の開発に取り組んできたが、今はAIが料理の組み合わせ(献立)や新レシピを考案してくれ、実際にカフェやレストランで提供される事例も増加。また、レストランで撮った食事写真をAIに入れるとその作り方を提示してくれる。技術面では「冷凍食品の進化」が止まらない。これまで手作り信仰が根強かったイタリアやインドの一般家庭でも冷凍食品は広く普及している。とはいえ一手間はかけたいニーズをカバーするために「ワンパンミール」が人気で、ワンパンミールであれば、食材をカットする手間が省け、フライパン1つで調理が完結するため、ちょっとした手作り感は保ちながらも、調理の時間やコストを大幅カットできる。このようなミールキットが、日本はもちろん世界中で人気が拡大しているという。特に日本は単身者世帯が増える一方なので、ワンパンミールやミールキットに需要はますます増えると予測。「ドライ&フリーズドライ食品」も最新テクノロジーによって開発が進み「美味しい」が叶う災害時の備蓄食としての役割や、エンターテイメント性も求められるレベルに到達。
3. ヒューマンセントリック(Human-Centric)
環境負荷を減らすことは重要であるが、やはり食品選びにおいて人間の健康や幸福を重視する考え方も両立させなければならない。例えば、食品のラベルは「クリーンラベル」が人気を集め、消費者が直感的に理解できるシンプルなラベルデザインであることが重要だ。また、米国では食品添加物の規制が強化されていて、イギリスでも超加工食品への規制が進行しているなど、地球だけでなくヒトにも優しい食品であることが今まで以上に求められている。さらに「ヌートロピック食品(認知機能向上食品)」にも注目が集まる。ヌートロピック食品とは記憶力や集中力を向上させる食品のことで、日本ではすでに「きのこ」「イチョウ葉」「タウリン」「テアニン」「高麗人参」など、食経験が十分ある評価の高い食品や食品機能成分が世界でも注目されており、これらの食品や製品が海外でさらなる人気を博す可能性が十分にあるとした。また、ストレス社会を生きる現代人にニーズがあるのが「ムードフード(感情に寄り添う食品)」だ。「落ち込み」「リラックス」「陽気」「集中」など、気分や感情に応じた食品や商品選びがトレンドになりつつあると解説した。
4. フードダイバーシティ(Food Diversity)
人々の多様性に配慮した食品開発もどんどん進んでいる。例えば「糖尿病患者向けの食品やアレルギー対応食」「ADHDの人々の特性を活かした食品デザイン」などが欧米では人気だ。さらに、先進国の人々の共通の社会問題に「孤独」「孤食」があるが、これを解決するために北欧では「交流OK」のサインが付いた専用マグが採用されるカフェやレストランが登場し、このマグを使っている人であれば双方自由に話しかけられるなど、社会問題に食がアプローチする可能性を見せているという。また「ライフステージ別の栄養設計」という視点についても解説。食の研究が進むにつれ、私たちは年齢ごとに必要な栄養素が異なることがよく知られるようになっている。例えば脂質やプロバイオティクスなどは、種類が豊富にあるが、年齢ごとにマッチするものが異なる。赤ちゃん向けプロバイオティクス、シニア向けオイル、更年期向けのナッツなど、年代ごとに起こる特有の健康課題を解決する栄養食のニーズはますます高まる、と解説した。
5.大阪万博と未来の食
そしてまもなく開催となる2025年の大阪万博では、日本館が「藻類」や「大豆」をはじめとした新たなタンパク質源としての食品を紹介することが予定されている。日本発の持続可能な食文化の提案は世界から注目されているので、まだまだ大きなチャンスがある、とした。