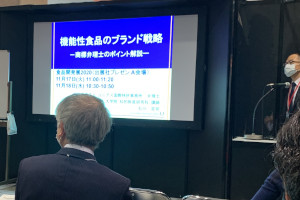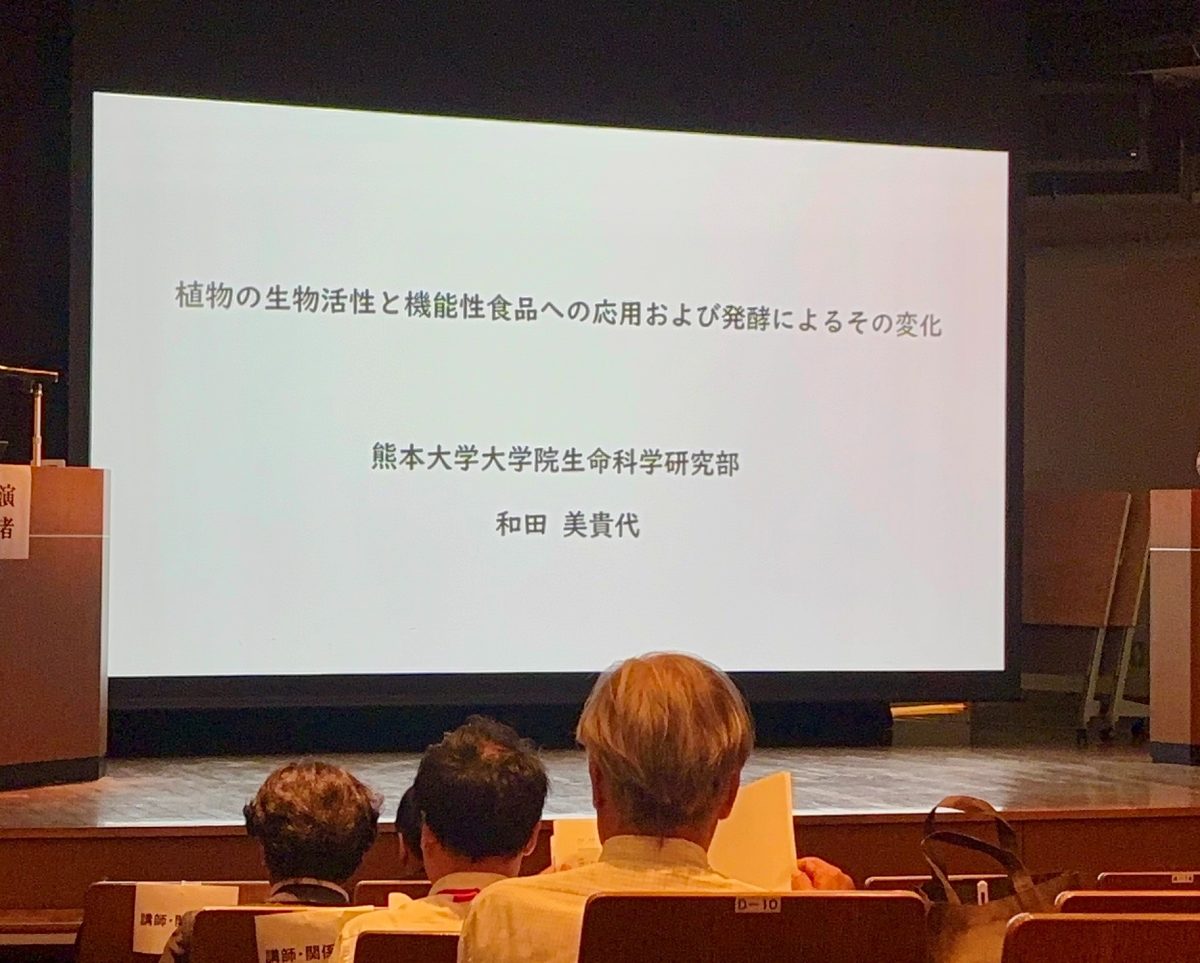
2025年6月27日(金)、第10回「日本黒酢研究会」が日比谷コンベンションホールで開催された。今回は「黒酢で導く健康寿命〜黒酢の温故知新と人生100年時代」というメインテーマをもとに6名の専門家が発酵食品の有用性や健康・予防医学に関する研究成果について講演を行った。ここでは熊本大学大学院 生命科学研究部 特任准教授 和田美貴代氏による「植物の生物活性と機能性食品への応用」を取り上げる。
熊本大学大学院 生命科学研究部 特任准教授 和田美貴代
本講演「植物の生物活性と機能性食品への応用」は、前半で「植物の生物活性」について、後半は「発酵による生物活性の変化の例」が取り上げられた。
和田氏は熊本大学大学院で植物生態学を主に研究しているが、植物生態学とは植物の生き方を研究する学問であり、その立場からも植物の機能性成分が植物自身や人間を含む周辺環境にどのような意味や役割を持っているのかについて強い関心を抱いていると話す。植物は大気中の二酸化炭素と水から、太陽光のエネルギーを利用して「糖、アミノ酸、タンパク質、脂質」などを合成する。これらは「一次代謝産物」と呼ばれ、植物の成長や生命維持に必要な基本成分を自ら賄っているが、一次代謝産物をもとに、さらにエネルギーを消費して複雑な経路を経て合成されるのが、いわゆる二次代謝産物である。では、植物はなぜこのようなエネルギーコストの高い経路を用いてまで二次代謝産物を作るのか。これを説明する映像資料が存在する、と紹介。一部の木が虫に食べられると、なぜか周囲の木々は被害を受けにくくなる。この理由として、被害を受けた木が特定の揮発性化合物(いわゆる精油成分)を空気中に放出し、それを周囲の木が受容することで防御反応を誘導する。つまり植物同士でコミュニケーションをとっている、というメカニズムが近年の研究で明らかになった、というものだ。植物が放出する揮発性物質には、アルファピネンや1,8-シネオールなど、私たちにも馴染みのある成分が含まれている。また、植物が自己防衛のために合成する毒性物質には、ニコチン、ソラニン(ジャガイモ)、トマチン(トマト)、アミグダリン(アンズの種)、アコニチン(トリカブト)などが挙げられる。これらは植物自身が自らの防衛のために合成している。さらに、カフェインやクロロゲン酸、カロテノイドなど、抗酸化成分として知られる物質も、植物にとってはストレスへの防御物質である。生物的ストレス(虫・病原体)だけでなく、紫外線や乾燥などの物理的ストレスへの防御にも寄与している。近年では、これらの物質が植物の成長や栄養吸収といった生命活動にも関与していることが明らかになっている、と解説した。二次代謝産物の種類は推定で20万〜100万以上とされているが、現在実際に測定・確認されているのはその10分の1〜100分の1にすぎない。
現在、植物の二次代謝産物はさまざまな機能性成分として私たち人間の健康にも貢献してくれているが、その代表が生薬といえよう。中国最古の薬学書『神農本草経』には、1年の日数と同じ365種類の生薬が記載されている。これを著したとされる神農は、自ら草木を食べて薬効を試し、毒にあたっては薬草で回復したという伝説を持ち、神として崇拝された。この書物に記された生薬の中には「老いに耐える」効能を持つものとして、ブドウ、オニバスの果実、サンシュユ、ゴマ、ケシの実などが挙げられている。現代においてブドウの皮には抗酸化成分が多く含まれることが明らかになっているし、現代西洋医薬も、これらの伝統的知識に基づいて発展してきた。たとえばケシからはモルヒネが単離され、ヘロインが合成された。ヤナギからはサリチル酸が見つかり、アスピリンが誕生した。タキサス属からは抗がん剤パクリタキセルが、ニチニチソウからはビンクリスチンやビンブラスチンが開発された。実際、1981年から2019年の間に承認された低分子医薬品のうち、完全に合成されたものは全体の3割であり、6割以上が天然物またはそれに由来する構造・情報を元にしたものである。
このような背景を持つ天然物は現在「機能性食品」にも用いられているが、これらを開発するはじめの手段が「スクリーニング」だ。熊本大学では現在「PD3(集落指向型植物データベース)」を構築し、ここには世界の35万種の植物情報が登録され、伝統使用情報や最新の薬効データも検索可能である。PubMedとも連携しており、論文検索も容易である。これは熊本大学発のベンチャー企業「シーハスプラス」が運営しているので興味がある場合は問い合わせてほしい、とまとめた。
後半では「黒酢」の便通改善効果と、発酵により植物の活性がどのように変化するかを示す事例として、株式会社アーデンモアの発酵製品「バンド酵母」の抗炎症活性に関する実験結果が紹介された。
現在、日本人の約1,000万人が慢性便秘に悩んでいる。発酵食品の効果が報告される中で、我々もその検証を行った。マウスにおいて「低繊維餌群」と「腸管運動抑制モデル」のそれぞれに黒酢を混合した餌とコントロールを与えて比較したところ、「低繊維餌群」と「腸管運動抑制モデル」のいずれも黒酢混合餌の方で便の水分量や個数、乾燥重量において増加傾向が見られた、と報告。特に「腸管運動抑制モデル」においては、腸管運動性の改善効果は認められなかったが、便の水分保持効果による排便促進が示唆され、黒酢には便の柔らかさを保つ効果が期待されるのではないか、と話した。 また、発酵処理による活性変化の事例として、西洋タンポポとヨモギの混合発酵製品「バンド酵母」の抗炎症効果について報告。細胞に対する脱顆粒抑制試験、マクロファージによるTNF-α放出抑制試験の2つを行ったところ、未発酵エキスでは細胞毒性が高かったが、発酵後は生存率が高まり、かつ脱顆粒抑制・TNF-α抑制が濃度依存的に確認されたという。発酵前はむしろ炎症促進作用もあったが、発酵によってそれが抑えられていたため、酵母と乳酸菌による植物エキスの発酵処理によって、植物エキスの抗炎症活性が高まり、同時に毒性を低下させた可能性がある、とした。活性成分は、元の植物成分の変化に加え、微生物が新たに合成した成分の可能性もあるので、今後さらに検討していきたいと話した。