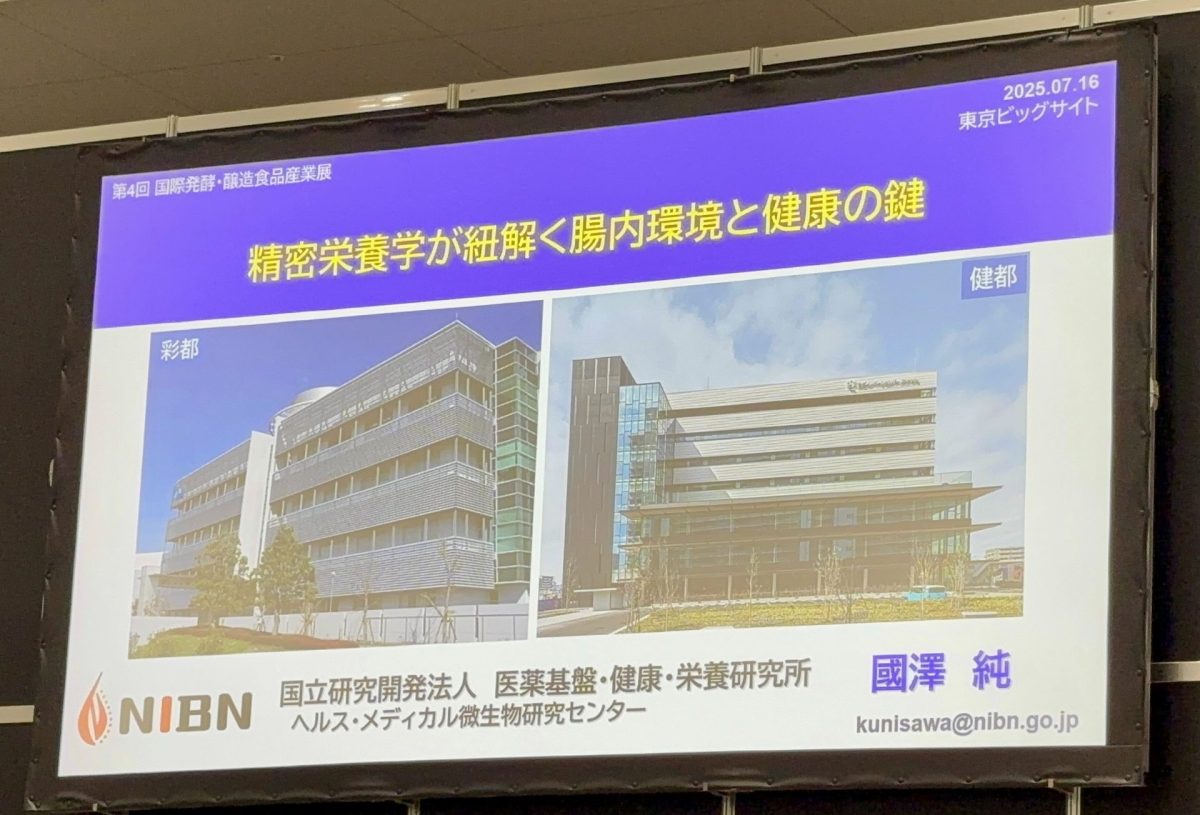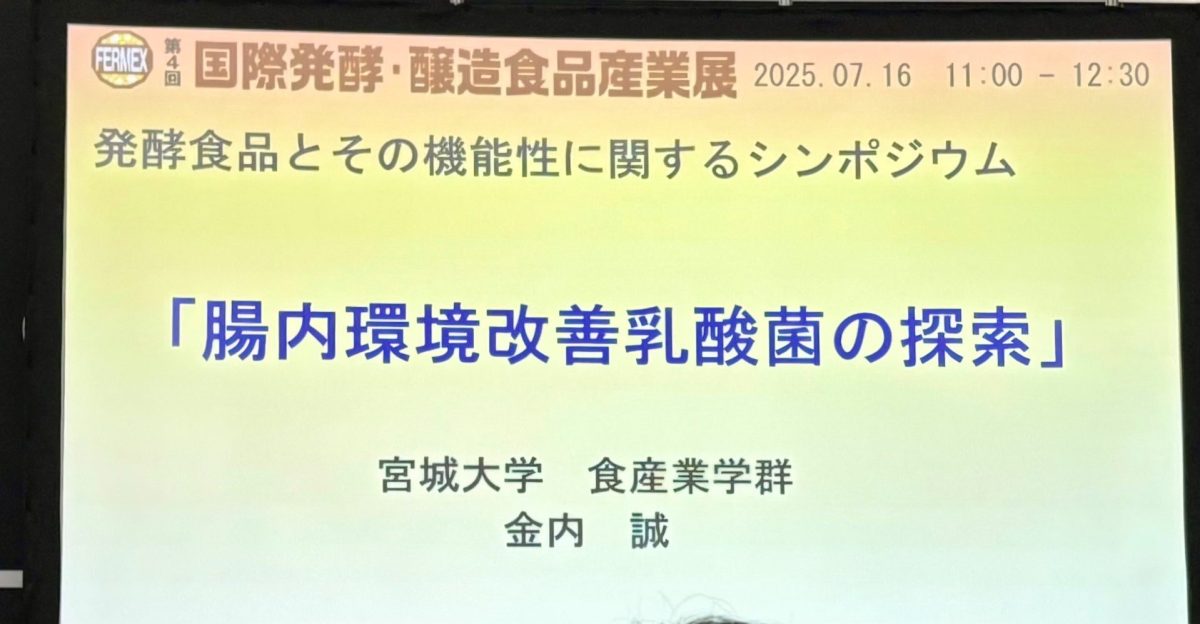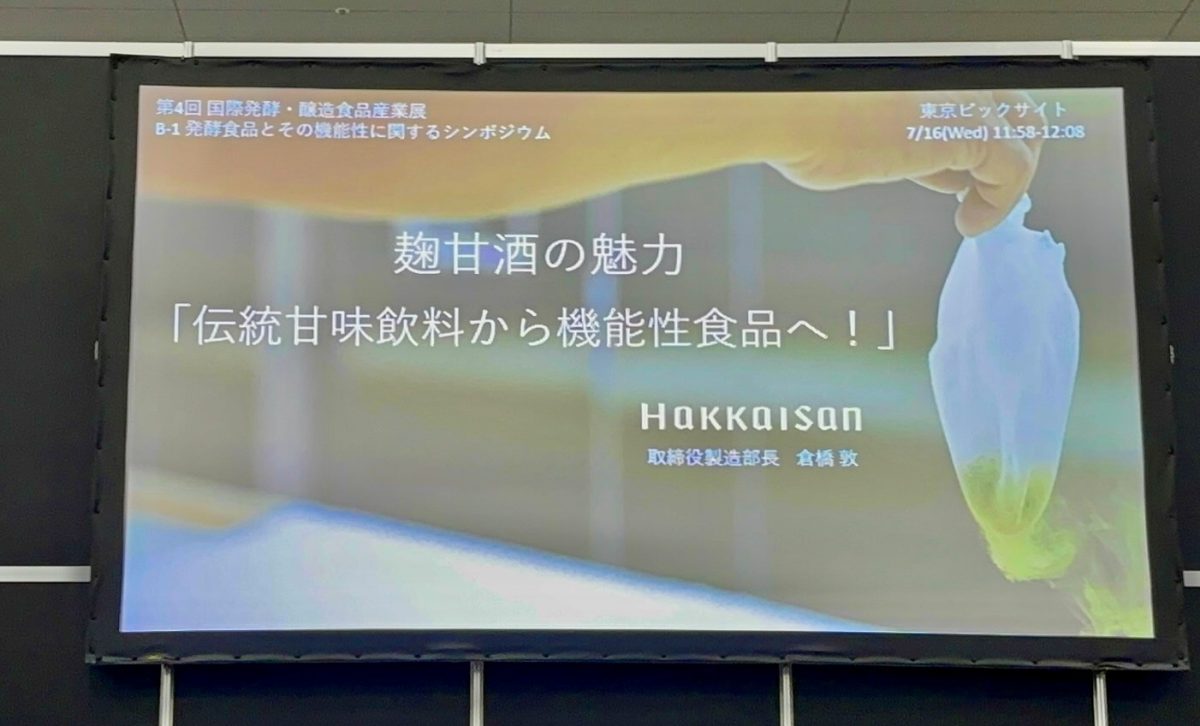
2025年7月16日(水)〜18日(金)、東京ビッグサイトにて「国際発酵・醸造食品産業展セミナー」が開催された。『国際発酵・醸造食品産業展』は、発酵・醸造に関わる食材、素材、研究機器、製造設備、検査機器、パッケージ製品などを一堂に集めた日本唯一の専門展示会で、2013年に「和食」2024年に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され以降、日本の発酵・醸造業界への関心は年々高まっている。ここでは「発酵食品とその機能性に関するシンポジウム」より、八海醸造株式会社取締役製造部長 倉橋敦氏による講演「麹甘酒の魅力『伝統甘味飲料から機能性食品へ!』」を取り上げる。
八海醸造株式会社 取締役製造部長 倉橋 敦 氏
八海醸造株式会社では醸造技術を通じ様々な日本酒を製造している。現在は世界飲料への挑戦として、国内だけでなく海外でも醸造を行い、日本酒のみならず焼酎、ビール、ウイスキーなども製造している。日本酒の製造において重要なのが麹であり、それを用いて甘酒の製造も手がける。甘酒を製造するようになったことでノンアルコールの商品も作れるようになり、機能性表示食品への展開に繋がった。
甘酒は日本の伝統的な健康飲料で、江戸時代には現在と同じような製法で作られ、行商も存在していた。八海醸造の甘酒は麹と水だけで作り、蒸したお米は一切入れない。日本酒と同様に、精米歩合60パーセントのお米を使い専用の麹を製造している。それによって誕生した麹甘酒が麹菌で初めてかつ唯一の機能性表示食品として登録された。現在のところ、他に麹菌を用いた機能性表示食品は登場していない。
麹甘酒で機能性表示食品を目指したきっかけは、甘酒ブームが起きた際、消費者から「お通じが良くなった」「肌がきれいになった」といった嬉しい声が多数寄せられたことにあった。もちろん「甘いので太らないか」「血糖値は大丈夫か」といった懸念の声も多く寄せられた。ところが甘酒に関する科学的な文献がほとんど存在しないという状況に直面し、メーカーとして、科学的にきちんと検証していく必要があると感じたという。文献調査をするも、甘酒に関する研究はほとんどなく、現在でも全世界で20報程度の論文しかない。そのうち5報は八海醸造の論文で、他の発酵食品に比べて甘酒の研究は遅れている。機能性表示食品の届出数を見ると乳酸菌やビフィズス菌の届出数が非常に多いのに、麹菌単体での届出は八海醸造の1件のみ。米麹や様々な麹由来の成分を使ったものは登録されているが、麹菌そのものではない。そこでSR(システマティックレビュー)ではなく、RCT(ランダム化比較試験)で研究を進めたという。
甘酒のプラセボは長らくグルコース水溶液などで代用されていたが、それは適切なプラセボではないと判断し、八海醸造では「米と麹」を製造してプラセボとして用いる。麹から作った麹甘酒とこのプラセボを比較して、2つの機能性を確認したという。
まず実感の声が多かった便通改善効果について。甘酒とプラセボを1日約100cc摂取する試験を行った結果、甘酒飲用群はプラセボ飲用群と比較して、便通が改善し、飲用開始から2週目、3週目、そして飲用を終えた後の4週目まで統計的に有意な差が見られた。また、腸内細菌叢を見ると便通改善効果に伴い「ブラウディア属菌が減少し、バクテロイデス属菌が増加」という結果が見られたと報告。麹菌は本来、生きている状態ではプリプリとしているが、甘酒は熱殺菌をして提供しているため菌は死滅する。死滅することで菌体は収縮するが、糸状の形は残る。この死滅した麹菌体が食物繊維のような動きをしているのではないか、とメカニズムについて推測した。さらに麹菌で機能性表示食品に登録されたものが他になく、乳酸菌のように「〜株」といったものが世の中にない中で、「HJ1株」という独自の株を設定。甘酒に含まれる麹菌体量は、使用する麹の量によって大きく異なる。麹だけで作った甘酒もあれば、お米を増量剤として入れているもの、酒粕を使っているものもある。これらの製品では麹菌体の量が非常に少ないため、甘酒の中にも「体に良い甘酒」と「そうでない甘酒」が出てくる可能性がある、と話した。
もう一つが肌の保湿効果について。「甘酒を飲んでいると、乾燥しない」という声が聞かれたため、甘酒とプラセボを8週間摂取してもらう試験を行った。1月から3月に実施したのだが、甘酒を飲んだ群はプラセボ群と比較して、肌の水分量が維持され、乾燥が抑制されることが確認できた。
これらの効果が麹菌のどこに起因するのかについて、麹菌の細胞膜中に含まれるグルコシルセラミドが肌の保湿に寄与し、外側の細胞壁を構成するグルカン複合体が便通改善に作用していると推測しているという。
今後取り組みたいのは、免疫機能やストレス対応の領域だと話す。動物実験でマウスにストレスを与えると、通常はフィールドの中央部に出てこなくなる(青い線はマウスの移動軌跡)。しかし、米麹を継続的に与えたマウスでは、同じストレスを与えても中央部に出てくるようになることが確認されており、これは抗ストレス効果が出ていることを示唆している。 現在、麹甘酒市場は概ね200億円を下回るような状況で、他社の参入が少ないという難しい状況にある。しかし今後、麹甘酒だけでなく、麹菌そのものの研究がもっと進んでいくことを期待している、とまとめた。