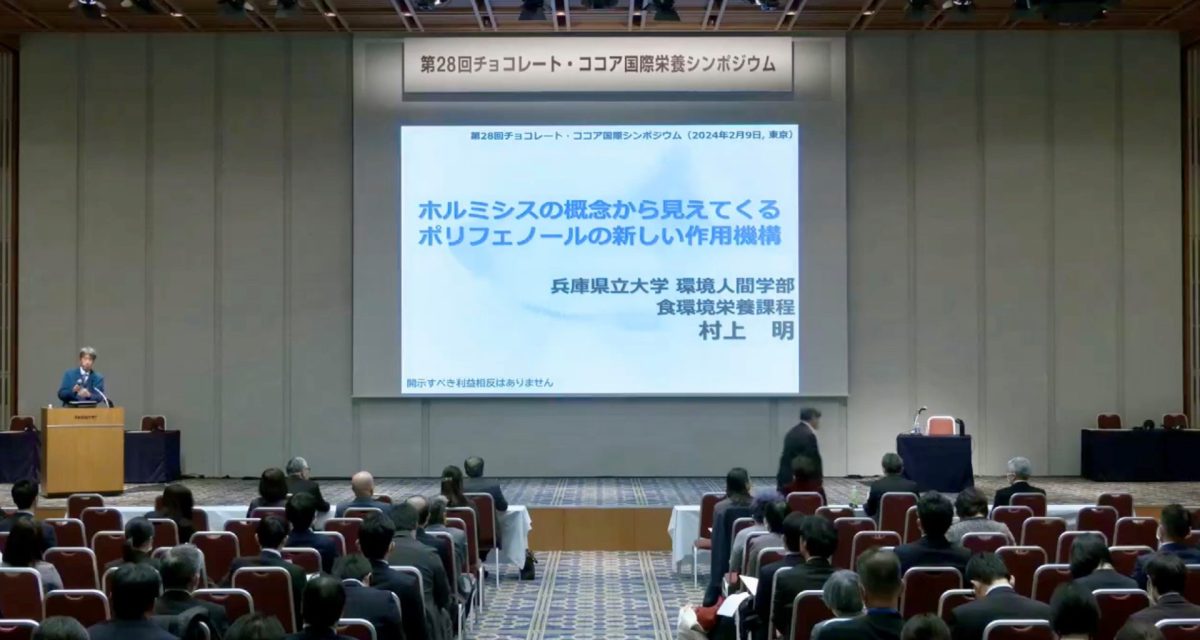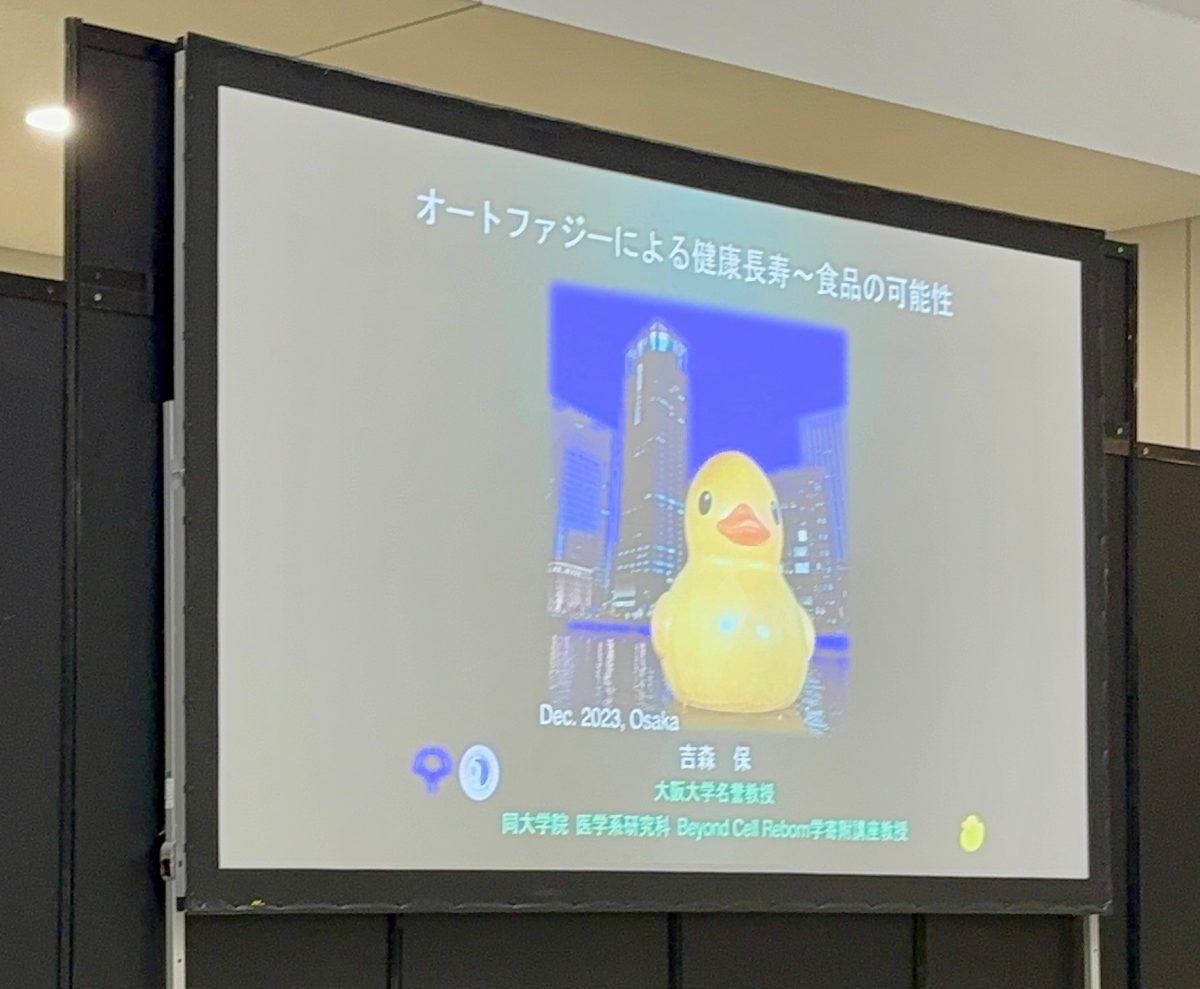
2025年10月15日(水)〜17日(金)、東京ビッグサイトにて今年で36回を迎える「食品開発展2025」が開催された。今年は出展社数が過去最大の671社となり、来場者はのべ4万人と報告されている。食品、飲料、菓子、健康食品などに利用される新素材や注目の機能性成分など、さまざまな最新技術の紹介や国内外のトレンドについてのレポートが活発に行われた。ここでは大阪大学名誉教授 吉森保氏の「オートファジーによる健康寿命〜食品の可能性」を取り上げる。
日本オートファジーコンソーシアム理事 吉森保
「生命とは何か」と尋ねられると、生命科学者は「命とは細胞である」と断言する、と吉森氏は話す。人間であれ微生物であれ、すべての生き物は細胞からできており、1つ1つの細胞は目に見えないが、細胞こそが生命の基本単位であると語る。そして、人間の体は約37兆個の細胞で構成され、一つひとつの細胞が生きている。さらに重要なのは、細胞一つひとつに、その人間一人を作り上げるのに必要なすべての遺伝情報(設計図)が格納されているという事実だ、と吉森氏。この情報があれば、理論上、そこから個体全体を再生することが可能であり、実際羊のクローンは作られている。この生命の基本に立ち返ると、病気や老化といった現象はすべて細胞レベルで起こっている。細胞の外から原因が加えられるが、細胞そのものに原因があるので、健康とは「細胞が常に正常な状態を保っていること」に他ならないと解説。
オートファジーの二大機能
そしてこの細胞の健康を根底から支えるシステムこそが「オートファジー(自食作用)」である。ギリシャ語で「自分を食べる」という意味を持つシステムは、細胞内に備わる極めて精緻なリサイクル工場兼防衛システムだ。オートファジーの発見は1950年代に遡るが、その複雑な仕組みの解明は難航。長く研究が低迷していた。2005年頃から研究が急加速し、2016年に大隅良典博士のノーベル賞受賞によってその重要性が世界的に認知される。そして吉森氏は大隅氏とともに初期の段階からオートファジー研究に携わっている。このオートファジーの役割は多岐にわたるが、特に重要な役割は次の二点に集約される、と吉森氏。
オートファジーは、細胞内のタンパク質やミトコンドリアなどの部品を日々、少しずつ取り壊し、新しい部品に作り替える役割を担う。車に例えるなら、故障してから修理するのではなく、毎日少しずつ部品を新品に交換し続けることで、常に車を「新車」の状態に保つ行為に等しい。細胞内の部品は、壊れたものだけでなく、新品であっても自動的にランダムに交換される。つまり理論上、細胞は常に「新品に近い状態」が保たれている。交換対象となった部品は分解され、分解されたものからはアミノ酸などの素材が得られ、これらは100%再利用されるため、極めて効率的かつ省エネで細胞の品質は常に維持される。この恒常的な新陳代謝こそが、細胞を若く保つ根源的な仕組みだ、と解説。動物実験では、オートファジーを人為的に停止させた場合、脳では認知症、心臓では心臓病など、各臓器で病気が発生し、全身で停止させれば死に至る。この事実は、オートファジーが生存と健康維持に不可欠であることを揺るぎない事実として示している。
オートファジーは、細胞を外敵や内部の有害物質から守る防衛システムとしても機能する。細胞内に侵入したウイルスやバクテリアなどの病原体を認識し、膜で包み込んで消化・殺菌することで、細胞を感染から守る。また、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の原因となる脳細胞内の異常なタンパク質の塊を標的として除去・破壊する役割も担う。特に脳細胞は一生入れ替わることがほぼないため、この除去機能は特に重要である。さらに傷ついたミトコンドリアは、細胞を傷つけたり殺したりする活性酸素を放出するが、オートファジーは損傷したミトコンドリアを選択的に除去することで、細胞を自己破壊から守ってくれている。
オートファジーのブレーキ役「Rubicon」の発見
これほど重要なオートファジー機能が細胞に備わっているにもかかわらず「人間はなぜ老い、病気になるのか」という疑問が生じるだろう。現時点では、加齢に伴いオートファジーの活性が低下することが、老化現象の核心にあると科学的に考えられている。そして、吉森氏の研究室では、この活性低下を引き起こす「ブレーキ役」のタンパク質を特定し、それが「Rubicon(ルビコン)」だと説明。Rubiconは、細胞の加齢に伴って必要以上に増加し、オートファジーの働きを過剰に抑制してしまう。これが老化に伴うオートファジー活性低下の主要因の一つだ、と吉森氏。このメカニズムを逆手に取ったのが、老化の制御を目指す実験だ。Rubiconを持たないように遺伝子を破壊したモデル生物(線虫やハエ)を作製したところ、 線虫では寿命が約1.2倍に延伸。また、 老化によって動かなくなるモデル線虫の運動機能が回復。これは、人間に例えるなら「80歳を超えてもフルマラソンを走れる」状態に相当するイメージだという。そして、 アルツハイマー病やパーキンソン病、加齢黄斑変性(失明原因第一位)、慢性腎症、骨粗鬆症など、軒並み様々な加齢性疾患の症状が抑制された、と解説。つまり「オートファジーを人為的に活性化できれば、単一疾患だけでなく、複数の加齢性疾患を一度に抑制できる」という、従来の薬の概念を覆す可能性を示唆している、と吉森氏。老化は、もはや必然ではなく科学的に制御可能な対象であるという認識が持てる、と話した。
健康寿命の延伸とビヨンドエイジングの時代
日本の平均寿命は世界トップクラスだが、健康上の問題なく日常生活を送れる健康寿命との間には約10年の差があるというのはよく知られている。この「不健康な10年間」をなくし、健康寿命を平均寿命に近づけることが、研究者にとっても医療財政の破綻を防ぐ社会にとっても急務の課題だ。オートファジーの活性化は、この健康寿命の延伸を実現するためのコアメカニズムであり、そのアプローチは単なるアンチエイジング(老化抵抗)ではなく、ビヨンドエイジング(老化を超越する)の概念へと進化している。私たちは、生命は全て老いを避けられないと思っているが、地球上にはハダカデバネズミやベニクラゲ、アホウドリのような極めて老化が遅い生物が確認されている。
そこで、老化の原因であるRubiconの増加を防ぎ、オートファジーを活性化させるための方法は、創薬だけでなく、日常的な食品や生活習慣にもないのか、研究はさまざまな角度から進められている。現時点でわかっているのは「カロリー制限」だ。 動物実験においてであるが、カロリーを制限することがオートファジーを活性化し、寿命を延伸することは確認されている。そして食品成分の探索も行われており、 科学的エビデンスに基づき、オートファジーを活性化する食品成分のスクリーニングを行っているが、現時点では徳島県の伝統的なお茶である乳酸菌発酵茶「阿波晩茶(あわばんちゃ)」に、既存の活性化薬物を凌駕する強力なオートファジー活性化能力があることが判明している、と解説。阿波晩茶は徳島県エリアで昔から愛飲されている伝統的なお茶で、微生物発酵との関係も調べているという。現在、阿波晩茶(あわばんちゃ)を使った臨床試験では、老化によって活動量が低下したモデル生物にエキスを与えたところ、活動量が回復し寿命が延伸するという、老化の可逆性(若返り)を示す結果が得られているという。他にも、熟成したチーズや納豆、椎茸、豆腐などに豊富に含まれるスペルミジン、柘榴やベリー、胡桃などに含まれるウロリチン、赤ワインやブドウに含まれるレスベラトロール、さらにアスタキサンチンやカテキンなどにもオートファジー活性作用が見られると解説した。
オートファジーの基礎研究は、大隅博士をはじめ、日本が世界を圧倒的にリードしているが、その研究成果を社会に実装する特許や製品化の動きは、海外、特に欧米や韓国に後れを取っている。この状況を打破するため、吉森氏らは大学発ベンチャーを設立し、オートファジー研究の成果を社会に還元する活動を推進している。具体的には、Rubiconを標的とした新薬の開発を進める一方、阿波晩茶エキスなどの科学的根拠(エビデンス)に基づくサプリメントの開発・製品化、ルビコンを指標としたオートファジーレベルの測定などである。現在、老化の可逆性を示す国際的なコンペティション「X-Prize」にも挑戦中で、この試験では、阿波晩茶エキスを含む複数の介入を通じて、ヒトの認知力・免疫力・筋力などの指標が「10歳若返り」することを報告しているという。最終的には、個人の努力や製品に依存するだけでなく、オートファジーの活性レベルを測定・評価する技術を開発し、全国の健康診断の項目に「細胞の老化度」を加えることも目標だと話す。 オートファジー研究は、人々に科学的な知識を提供し、「なぜ病気になるのか」「どうすれば健康でいられるのか」という問いに対し、細胞レベルからの明確な答えを提示することで、社会全体の健康と科学的リテラシーの向上に貢献していきたい、とまとめた。