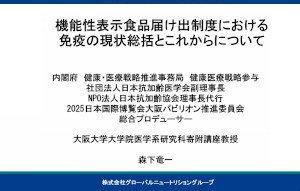2025年6月16日(月)〜6月27日(金)、オンラインで「食品開発展プレゼンフォートナイト」が開催された。食品開発展プレゼンフォートナイトでは、オンライン上で機能性素材や新技術などのプレゼンを聴講できる。こではLycored株式会社による「抗酸化作用を持つカロテノイド:リコピンとルテインの機能性表示申請と市場動向」を取り上げる。
Lycored株式会社
本講演では、機能性表示食品に関する最新のトレンドと市場動向について説明と、ライコレッド社の主要成分であるリコピンとルテインについての最新情報が報告された。
機能性表示食品市場は拡大を続けている。2023年の機能性表示食品市場は前年比19.3パーセント増の6865億円となった。さらに2024年前半にはサプリメント市場全体に落ち込みが見られたものの、後半には再び市場拡大が進み、2024年全体では5.2パーセント増の7274億円に達する見込みである。消費者の購買行動においては、若年層からの関心が高くなっていることは良い傾向であるが、その分これまで以上に信頼性が鍵となる。特に20代男性を中心とする若年層が機能性表示食品に強い関心を示していることは見逃せない。20代は美容・健康への意識が高く、これまで以上に「身体に良いもの」「機能性があるもの」を求める傾向が高まっているからだ。
また、健康食品の中でも美容サプリメント市場は2500億円を超え、機能性表示食品の届け出数は現在までに800件を突破している。企業の動向としては、化粧品メーカーが新市場開拓を目的にインナーケア領域に力を入れており、例えば資生堂も資生堂ビューティーウェルネスというインナー事業に参入した。また、美容大国の韓国ではインナーケアの低年齢化が進んでいて、これをきっかけに日本でも若年層のインナーケアへの関心がますます高まることが予測される。
「スマホ老眼」という言葉があるが、スマートフォンやタブレットの普及により、若年層から高齢者まで幅広い世代で眼精疲労や視力低下が社会問題になっている。機能性表示食品においても、全体の約8パーセントにあたる121品がアイケア用途になっているのだ。注目の成分として、ルテイン・ゼアキサンチン・ビルベリーがある。製品の傾向としては、ルテイン&ゼアキサンチン、ルテイン&ビルベリーなど成分を複数組み合わせた製品が多く、複数の成分を配合することでより高い効果を訴求する商品が増えている。
現在、ライコレッド社では4件の機能性表示を申請しており、そのうちの2件がルテイン&ゼアキサンチンの組み合わせによる成分だという。1つが「ルテイン10mg+ゼアキサンチン2mg」で「紫外線やブルーライトなどの光ストレスから目を保護する」、もう1つが「ルテイン20mg+ゼアキサンチン4mg」で「光ストレスから目を保護する」に加え「ぼやけやかすみを軽減しくっきり見る力を改善する」「目の疲労感を軽減」というヘルスクレームだ。いずれも近日受理予定だが、異なる含有量で設計することで、幅広い商品化を狙っている。またリコピンについては、1つは機能性関与成分を22mgで設計し「悪玉コレステロールの低下」というヘルスクレームで受理されている。現在申請済みで近日受理予定なのがリコピン16mgで、こちらは「紫外線刺激から肌を保護する」というヘルスクレームにしているという。
ライコレッド社では、種の育成から原料の農園管理までを一貫して行なっているが、これまでのリコピンの利点を超える「ライコマト6(Lycomato6)」を開発提供することにも成功している。ライコマト6は標準化されたトマト抽出物であるが、これまでのリコピン単体に加え、フォトエン、フィトフルエン、トコフェロール、フィトステロール、ベータカロテンなどの植物栄養素を豊富に含んでおり、これらが相乗効果を発揮して「肌の健康」「免疫の向上」「血圧の改善」「目の健康」「酸化ストレスマーカー減少」「骨吸収マーカー減少」といったさまざまな範囲での高い効果を示すことが臨床試験で確認されているという。マリーゴールド由来のカロテノイドについても「Lyc-o-Lutein HZ」という原料の規格化に成功している。これは、米国国立眼科研究所が最新のガイドラインで「ルテインは少なくとも10mg、ゼアキサンチンは少なくとも2mgを毎日摂取する」ことを推奨、この摂取量で黄斑色素密度を高めることを臨床的に示し、眼の保護機能をより強化する効果が期待できる、という。「Lyc-o-Lutein HZ」はこの推奨摂取量をカバーするために設計されていて「ルテイン10mg+ゼアキサンチン2mg」になっている、と解説した。 今後、機能性表示食品は「クロスカテゴリー化」、つまり健康×美肌や、健康×腸内環境の改善や、目の健康×ストレスケア(例えばギャバなどを組み合わせるなど)など、一つの製品で複数の効果が得られる方向に向かうことが予測される。忙しい消費者は、1つの製品で多くの効果が欲しいというニーズを持っているためだ。このように同じ成分でも異なる成分含有量で機能性表示食品の届出を行うことで、原料として今後より多くの展開が期待できるのではないかと話した。