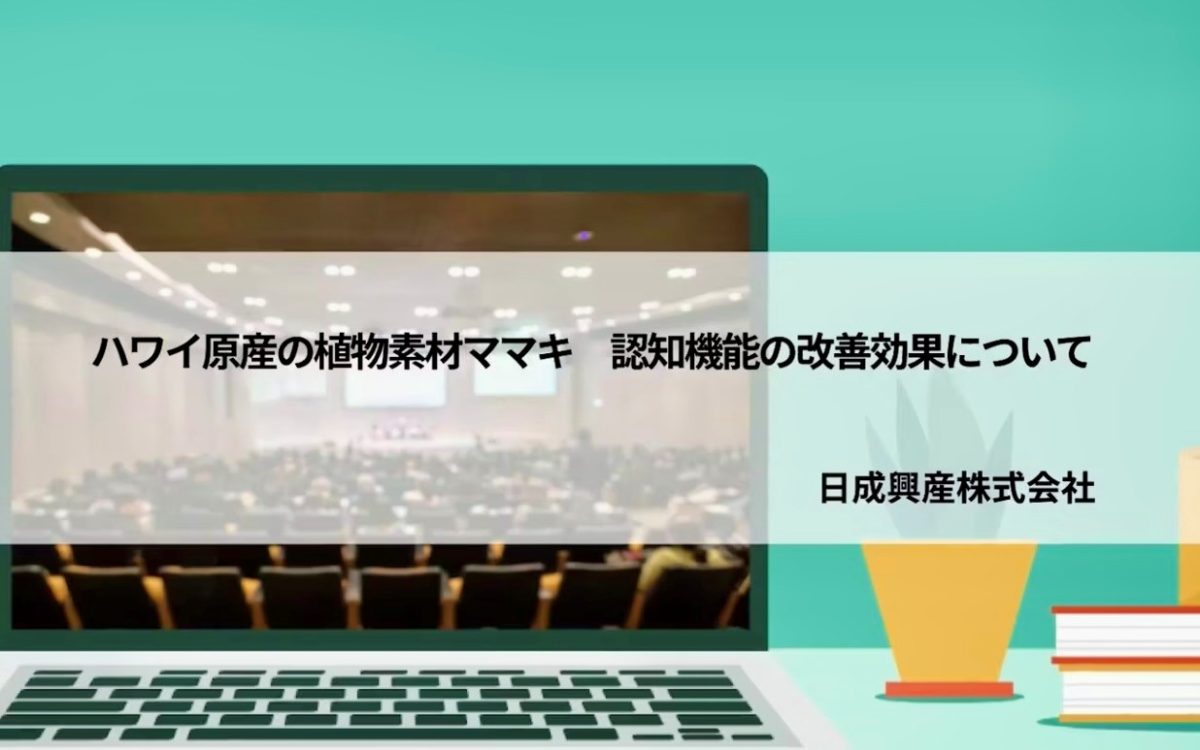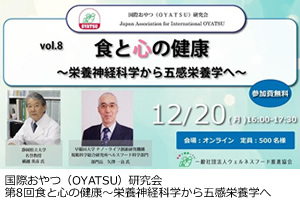2025年10月24日(金)、ニューピアホール(東京都港区)にて公益財団法人ヤクルト・バイオサイエンス研究財団主催の「第33回腸内フローラシンポジウム」が開催された。腸内フローラやプロバイオティクスという言葉は日常にも浸透するレベルに至っているが、そこからさらに踏み込み、本年は腸内フローラとニューロサイエンス(脳腸軸)の関係性をテーマにシンポジウムが開催された。腸内細菌叢が自閉症や認知機能低下などの神経発達障害やパーキンソン病などの神経変性疾患に与える影響、そして腸内細菌叢の恒常性に与える影響について、腸内細菌叢研究の最前線で活躍する7 人の専門家による講演が行われた。ここでは米国カリフォルニア工科大学Sarkis K. Mazmanian氏による「パーキンソン病の原因及び治療標的としての腸内マイクロバイオーム」を取り上げる。
カリフォルニア工科大学 Sarkis K. Mazmanian
これまで、パーキンソン病(以下PD)は、手足の震えや歩行障害を特徴とする「脳の運動障害」として認識されてきた。しかしその病態は脳内に留まらず、発症の数十年も前から便秘などの症状として現れることが知られており、この現象は多くの研究者の間で謎とされてきた、とMazmanian氏。しかしPDと胃腸症状に関する知見は、初めてパーキンソン病が詳細に記述された論文「振戦麻痺に関するエッセイ」(1817年、ジェームズ・パーキンソン著)にも報告されていたことが知られる。今回Mazmanian氏らは、この謎の核心に迫る研究成果を発表。パーキンソン病の病理を引き起こすα-シヌクレイン(α-Syn)の異常凝集に、腸内細菌が産生する細菌アミロイドが直接関与していることを動物モデルで証明。さらに、この細菌アミロイドの凝集を阻害する経口薬「AX-5006」が、既存の症状と凝集体を消失させるという画期的な治療可能性を示した。
パーキンソン病は、脳の黒質にあるドーパミン産生神経細胞内でα-シヌクレイン(α-Syn)というタンパク質が異常に凝集し、「レビー小体」を形成することで神経変性を引き起こす。このα-Synの凝集は運動症状が現れる20年前には便秘として、10年前にはレム睡眠行動障害として現れることが疫学的に示されている。この時間差から、PDの発症には少なくとも二つのパターンが存在するという仮説が提唱されている。つまり「Body First型」として、病理が腸管神経系で始まり迷走神経などを経由して脳に上がっていく経路で、初期に顕著な胃腸症状を伴うパターン。もう一つが「Brain First 型」で、病理が脳内で始まり末梢に広がるパターンだ。このうち、腸で病理が始まる「Body First型」においては、特に「腸脳相関」を利用したアプローチこそがPDの根本的な理解と治療に不可欠であると強調。実際に、米国、欧州、日本、韓国など世界中のコホート研究で、PD患者の腸内細菌叢が健常者と異なるディスバイオシスを示すことが共通認識されている。これはPDに特有な腸内細菌が存在する可能性も示唆していて、将来は診断マーカーとしての応用も期待されている。
Mazmanian氏の研究チームは、ヒトのα-Synを過剰発現させる遺伝子改変マウス(PDモデル)を用いた実験を行ったところ、以下のような結果が得られたと発表。
まず、PDモデルマウスは、運動機能の低下や、ヒトの便秘に相当する胃腸症状を示した。しかしこのPDモデルマウスを無菌環境(GF)で飼育し、腸内細菌叢を除去したところ、運動機能の低下も胃腸症状も消失。さらに脳を調べると、PDモデルマウスの脳内には広範囲にα-Syn凝集体が検出されたのに対し、無菌マウスでは凝集体が劇的に減少していた。この事実は「マイクロバイオームの存在が、PDモデルマウスの病理発症に必須である」という因果関係を明確に示したと言える。さらに脳内のα-Syn凝集が起こると、脳のニューロンにストレスを与えるため、ミトコンドリアの機能不全が起こる。実際、PDモデルマウスの脳細胞のミトコンドリアは過剰な活性を示していて、これはニューロン凝集に対するストレスの代償として過剰に働いていることを示唆している。しかしこのミトコンドリアの異常活性も、腸内細菌叢を除去した無菌マウスでは正常化していた、と報告。これは、腸内細菌が介在してα-Synの凝集が起こり、その結果として神経細胞に過剰なストレスがかかっていることを示しているのではないか、と解説。
Mazmanian氏は、腸内細菌叢を標的とした最初の介入として、プレバイオティクス(高繊維食)を用いた実験結果を発表。高繊維食は腸内細菌によって短鎖脂肪酸(SCFA)に変換される。PD患者ではこのSCFAレベルが低いことが報告されているが、高繊維食を与えたPDモデルマウスでは、運動症状の発症が予防され、脳内のα-Syn凝集も抑制された。この効果は、脳の免疫細胞であるミクログリアを介していることが示唆された。高繊維食を与えられたPDモデルマウスでは、ミクログリアの形態が炎症性の活性化から遠ざかる変化を示し、遺伝子解析では炎症誘発性遺伝子の発現が下方制御されたことが確認された。さらに、疾患の早期に保護的役割を果たすとされる疾患関連マクロファージのミクログリアの割合が増加。実際に、薬物でミクログリアを枯渇させると、高繊維食を与えても運動症状が再発したことから、このミクログリアの機能がプレバイオティクスの有益な効果に必須であることが示された。食事(高食物繊維食)による腸内環境の改善が脳の免疫監視システムを調節し、神経保護に働いているのである。
次に研究チームは病理の原因物質の特定に焦点を当てた。α-Synと同じく自己凝集性の構造を持ち、パーキンソン病患者の腸内で増加傾向にある大腸菌由来の細菌アミロイド「CsgA」に注目。このCsgAに宿主のα-Syn凝集を誘発する可能性が疑われるからだ。このCsgAを産生する大腸菌のみをGFマウスに投入したところ、運動症状の低下と脳内のα-Syn凝集が誘発された。一方、CsgAを産生しない変異大腸菌では、症状も凝集も誘発されなかった。この結果は「CsgA」がα-Syn凝集を誘発する鍵となる物質であり、PD病理の原因となることを強く示唆するのではないか、とMazmanian氏。さらに、CsgAの存在下ではミクログリアがより活性化し、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α)の産生も増加することも確認され、細菌アミロイドCsgAが脳の炎症にも直接関与していることが示唆される、と説明。Mazmanian氏らは、このCsgAに着目し、創薬企業と共同でCsgAの凝集を特異的に阻害する経口薬「AX-5006」を開発。
AX-5006は特殊な化学修飾を施すことで血流にほとんど入らず、薬効が完全に腸管に限定されるよう設計されている。薬物が脳や体内に広がることで起こる副作用のリスクを低減し、疾患の発症源である腸にのみ直接作用する。これは安全性の観点から極めて重要な特性だ。PDモデルマウスにAX-5006を投与した治療実験の結果は驚くべきものだったと、解説。運動低下症状を既に示しているマウスにAX-5006を経口投与したところ、10週間で運動症状が投与量に依存的に回復。さらに、脳内に既に形成されていたα-Syn凝集体も、経口薬の投与によって消去されることが示された。これは、腸を治療することで脳の病理が逆転し得るという、強力なメッセージではないか。この効果は、腸内でCsgAの凝集を阻止することで、脳への新たな病理の流れを断ち切り、その間に脳のオートファジーなど細胞内のデトックス機序が既存の凝集体を除去できるためだと推測されていると説明した。 Mazmanian氏は、これらの動物モデルでの証拠に基づき「腸を標的にした治療」がパーキンソン病に対する最も有望な戦略ではないか、と話す。薬物を脳に到達させるのは難しいが、PDのように疾患に腸の病態生理学的要素が関与している場合、薬物を腸内に作用させるだけで十分なのではないか。腸から脳へのシグナル伝達を改善することで、脳の症状を改善するという戦略の有効性を強調した。AX-5006は現在パーキンソン病の早期段階の患者を対象とした臨床試験への導入が計画されている。これが成功すれば、PD治療は従来のドーパミン補充療法から、疾患の根本原因にアプローチする新規創薬へと大きく転換し、「腸から始まる神経変性疾患」という新たな概念が確立されることになる。まさにパーキンソン病治療のパラダイムを「脳から腸へ」と根本的に転換させる可能性を強調した。